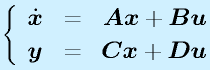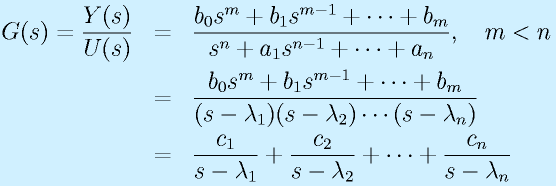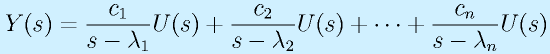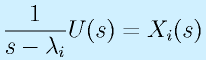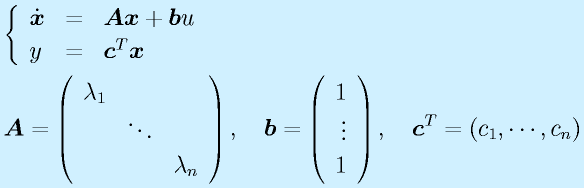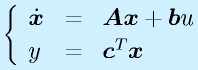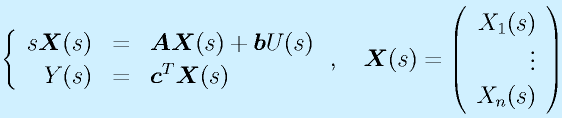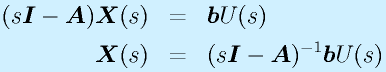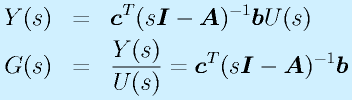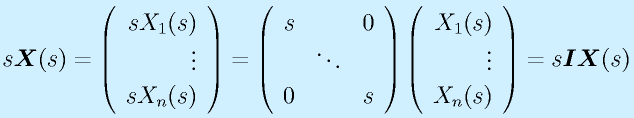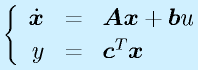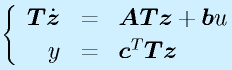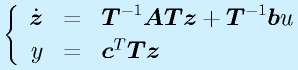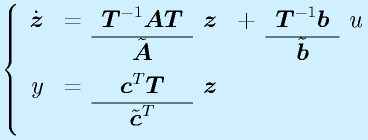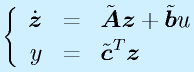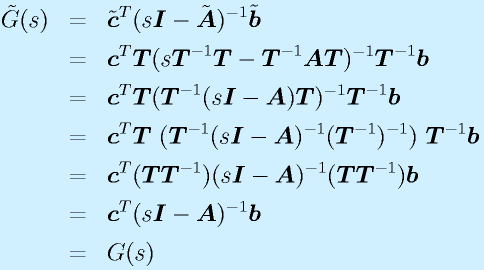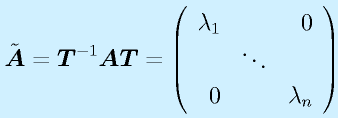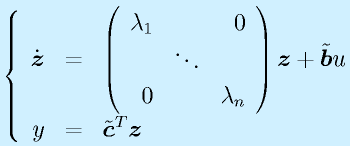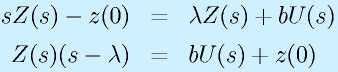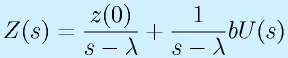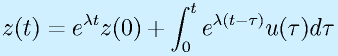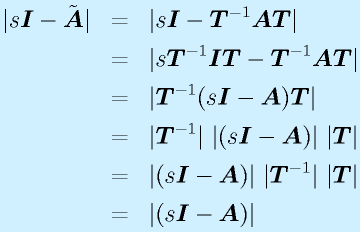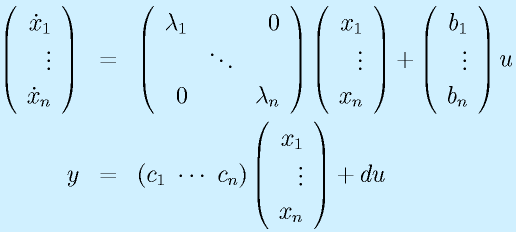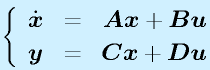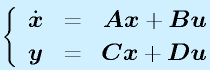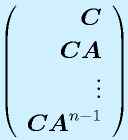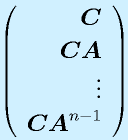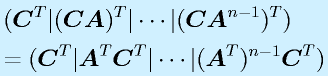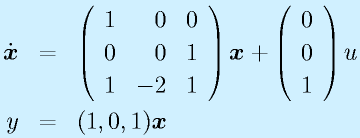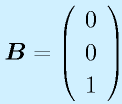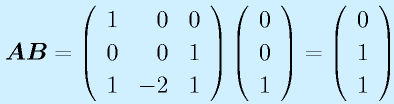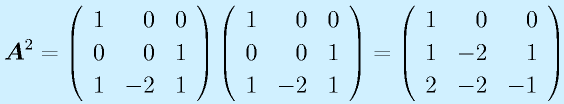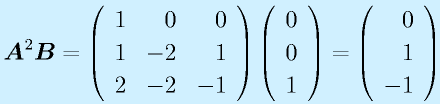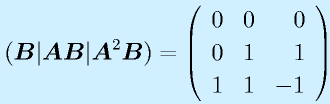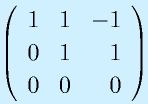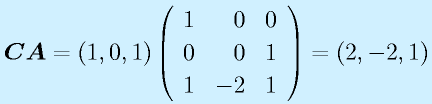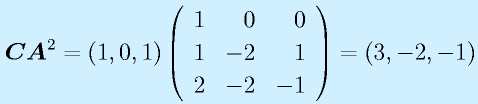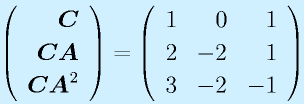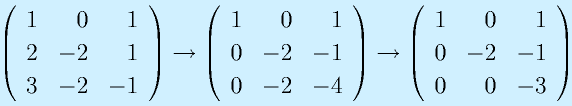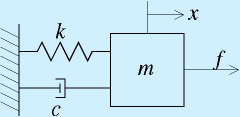 制御対象となる線形のシステムは、1階の連立部分方程式で記述できます。
制御対象となる線形のシステムは、1階の連立部分方程式で記述できます。
バネ・マス・ダンパ系(右図)を例にします。
運動方程式:
![]()
(この運動方程式は2階の微分方程式)
ここで、![]() とおくと、
とおくと、
![]()
となります。書き換えると
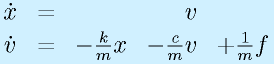
さらに、行列表記にすると、
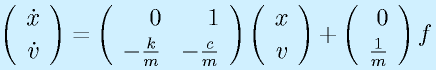
となります。ここで、
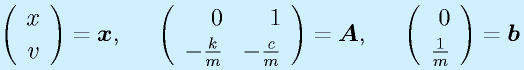
とおくと、
![]()
という形で表記できます。
この行列ベクトル形式で表示したシステムの方程式を 状態方程式 、ベクトル![]() を 状態変数 といいます。
を 状態変数 といいます。
こういったシステムを実際に作り、観測するとき、必ずしもすべての状態変数が見えるわけでもなく、また単独で見えないこともあります。これを一般的に表記すると、
![]()
と書けます。前半は状態変数が出力にどう出てくるかを示し、後半は入力が観測値に漏れてくる量です(一般にはあまりありませんが、そういうことも想定しておきます)。この方程式を 出力方程式 と呼びます。
例:上の例で位置が見える場合
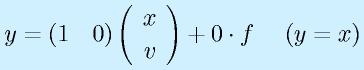
以上を一般的な形式で書くと
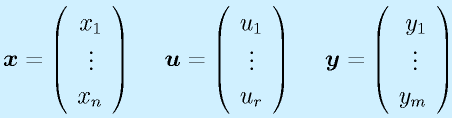
(入力x:n要素、出力y:m要素、入力u:r要素)
に対しても、
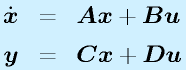
となります。ただし、
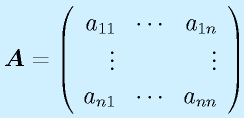 (n×n)
(n×n)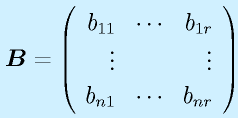 (n×r)
(n×r)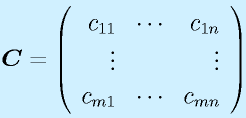 (m×n)
(m×n)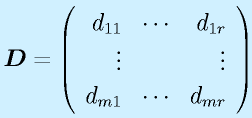 (m×r)
(m×r)です。
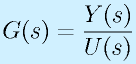 :出力のラプラス変換/入力のラプラス変換
:出力のラプラス変換/入力のラプラス変換