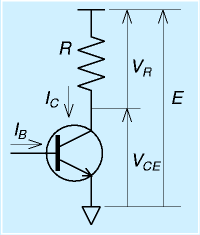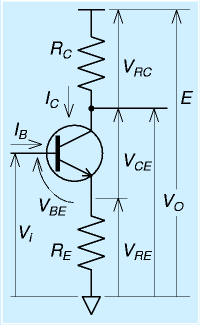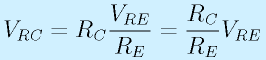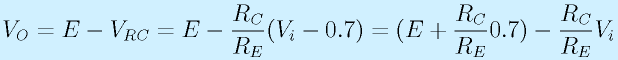ダイオードとトランジスタ
[| ]
最終更新: 2011/02/10 19:18:23
はじめに
この節ではバラ(デスクリート)の半導体部品である、ダイオード、トランジスタについて扱います。
バラの、と明示したのは、すでに半導体部品はメカトロIで出てきているためです。
ダイオードもちょっと出てきていましたが、アナログ回路で使用したオペアンプも、ディジタル回路で使用したロジック回路のたぐいも、一般にIC:集積回路として存在し、そのICが半導体でできているためです。
一般的な電子回路の教科書では、抵抗、コンデンサの次はダイオード、トランジスタと相場が決まっていますが、とくに使う当てもなかったので、メカトロIでは敢えて避けていました。実際、ロボットなどでセンサ回路をつくったりするときにトランジスタを使うことは少なく、ふつうはオペアンプを使います(簡単で、便利で、性能が良くて、さほど高いわけでもないから)。
しかし、メカトロIIではオペアンプやロジック回路では太刀打ちできないケースがでてくるため、まず、ここから始めます。
なおこのページを執筆するに当たり、大類重範著、日本理工出版会「アナログ電子回路」を読み、その知識を元に大幅に簡素化して表現しています(引用というにはずれてしまっているレベル)。
半導体とは
導体・絶縁体・半導体
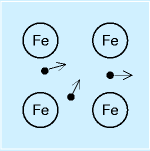 |
| 鉄の模式図。●で表した自由電子がうろうろしているので、電圧をかけるとプラス側に流れていき、電流となる。 |
おおむね、物質は電気的に2種類にわかれます。
- 導体:抵抗がとても小:電気がよく流れる(金属、イオンの入った水など)
- 絶縁体:抵抗がとても大:電気がほとんど流れない
これは小学校の実験にもあるような、単純な話です。
これらの違いは、自由に動く電子の有無によります。物質は原子からできていて、その原子は原子核と電子からなります。電子は原子核からある程度の距離に存在しますが、そのうち、一番外側の電子が物質の化合や結晶するときにつながる役目をする価電子と呼ばれる電子です。この電子がなにかの拍子(熱で振動したり)にはずれると自由電子となります。
この、価電子がはずれて自由電子になると、結晶の中を動けるようになります。電子はマイナスの電荷を持っているため、電子が一方向に一斉に流れた場合、外から見ると電流がその逆向きに流れているように見えます。
(電子とかの存在を知る前に電気が広まってしまったため、正負がこう決まってしまったような)
導体は、そのなかの原子の価電子がはずれやすい物質です。自由電子が多いため、電流が流れやすくなります。一方、絶縁体は価電子がはずれにくく、自由電子がきわめて少ないため、電流が流れにくいわけです。
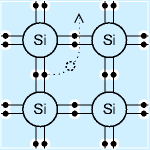 |
| シリコンの模式図。原子間で電子2個を共有して結合している。まれに電子がはずれて自由電子となり、電流がわずかに流れる。 |
さて、本題の半導体は、これらの中間にあたります。適度に自由電子ができやすい物質です。そのため、導体と絶縁体の間くらいの抵抗です。ちなみに、ふつうの「抵抗」と呼ばれている部品は、半導体とは別物とされています(定義からすると半導体っぽいですが)。もちろん、半導体でも「抵抗」をつくることができますが、ふつうの「抵抗」は自由電子が流れようとするとあちこちにぶつかって流れにくい、と説明されることもあります。ので、ここではおいておきます。
具体的には、半導体としてメジャーなものはシリコン(Si)、ゲルマニウム(Ge)などです。特殊なものとしては、ガリウムヒ素(GaAs)、炭素(ダイヤ、C)などです。いま、半導体製品といったら、ほとんどがシリコンで、特別な用途にゲルマニウムやGaAsがつかわれています。
n型半導体、p型半導体
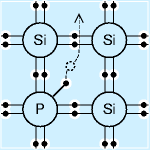 |
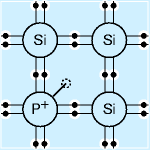 |
| 電子がSiより1個多いリンを混ぜると、電子が半端になってとれやすくなる。 |
とれた電子は電流のもととなり、とれた後は+になったリンが残る。 |
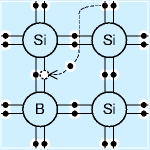 |
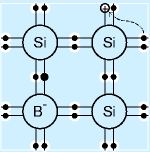 |
| 電子がSiより1個少ないホウ素を混ぜると、電子1個分隙間があき、電子を吸い込みやすくなる。 |
電子を周りから吸い込むとそこが、電子が抜けた+の穴=ホールとなってまた隣を吸い込む。ホウ素は−になる。 |
いわゆる、半導体部品(ダイオード、トランジスタ、ICなど)をつくるには、純粋な半導体物質にまぜものをして、2種類の半導体にして使います。
n型半導体とよばれる半導体は、シリコンにリンやヒ素をまぜて作ります。シリコンは価電子が4個で、隣り合うシリコン原子同士で1個ずつ出し合ってペアをつくって結合しています(ので、「隣」は4個)。これに対してリンやヒ素は価電子を5個もっています。この1個あまったのが、結晶のなかではずれやすい存在になります。その結果、n型半導体では電子が結晶内に転がっている状態、になりやすくなります。
p型半導体と呼ばれる半導体は、シリコンにホウ素、ガリウムを混ぜます。これらは価電子が3個で1個足りません。隣のシリコンはペア待ちになります。すると、ここが電子を近場から吸い込む現象がおこります。
吸い込まれたところは、マイナスの電荷の電子が足りなくなった穴になり、ホール(正孔)と呼ばれ、マイナスが足りないので局所的にプラスの場所になります。このホールは、隣の電子を吸い込んで(ホールではなくなる)、またとなりにホールを造ることになります。実質的には「電子が無い場所」ですが、見た目プラスの粒が動いていくように見えます。
以上、おおざっぱな解説ですが、n型半導体は「マイナスの粒が入っている物質で結晶はプラス」、p型半導体は「プラスの粒がはいっている物質で結晶はマイナス」、とだけ思っていれば、以下の話には十分です。
ダイオード
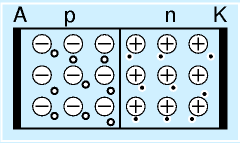 |
| ダイオード模式図 |
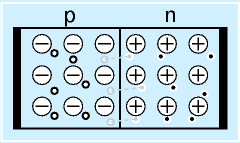 |
| 接合面近辺の電子とホールは対になって消滅する。 |
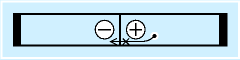 |
| 結果、接合面付近に正負の領域ができて、たとえば電子はp領域の負と反発し、n領域から近寄れない。 |
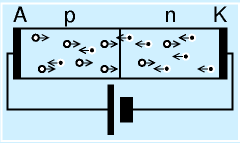 |
| 順方向電圧印加時 |
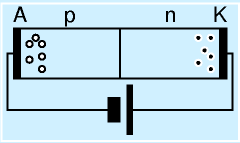 |
| 逆方向電圧印加時 |
このn型とp型の半導体をつなぎます。つなぐといっても、製造するときに接着するわけではなく、上記不純物を混ぜるときにうまく領域分けをします。これがダイオードです。
詳しく見てみます。
電子の浮遊するn型とホールのあるp型を接合すると、その近辺では適当に電子が動いた拍子にホールにはまって、電子とホールが対になって消滅します(逆にホールも動きます)。
その結果、接合面のそばでは、nでは結晶自体がプラスの、pではマイナスの性質が強くなります。すると、電子がマイナスな結晶と反発してpの側にいきにくく、ホールもnの側にいきにくくなり、対消滅が起こらなくなります。壁(正式には空乏層)ができたような状態で、これがダイオードになにもしていない状態になります。
ここでダイオードに電圧をかけてみます。p型にプラスの、n型にマイナスの電圧をかけてみます。この場合、結晶のプラスマイナスを超えてpの側に電子を、nの側にホールを引く力が強くなります。その結果、それらが互いの方向に流れ込む形で、電流が流れるようになります。
逆に、n型の側にプラスの、p側にマイナスの電圧をかけた場合、n型のなかの電子もp型の中のホールもそれぞれの電圧にひっぱられて、ますます接合面から遠ざかり、電流が流れることはありません。
これがミクロにみたダイオードの特性です。これを外から見ると、p側(アノード端子)にプラスの、n側(カソード端子)にマイナスの電圧をかけると、電流が流れ、逆向きだと電流がながれません。また、電流が流れるにしても、「壁」を突破するだけの電圧が必要となります。
この壁を突破する電圧は「順方向電圧降下」とよばれ、一般的に使われるシリコンのダイオードで0.6〜0.7[V]程度、以前使われていたゲルマニウムダイオードで0.3[V]程度です。逆にこの電圧をかけなければ電流は流れません。
ちなみに発光ダイオードLEDはダイオードに細工して、接合面付近で、流れてきた電子とホールが対消滅するときにそのエネルギーを光として出すようにしたものです。種類はいろいろあり、2[V]〜4[V]程度で光ります(青など波長の短いものほどエネルギーが大きいため、必要な電圧も高くなるようです)。
バイポーラトランジスタ
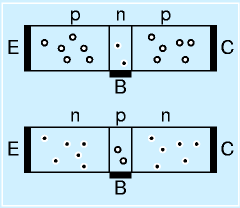 |
| トランジスタ模式図 |
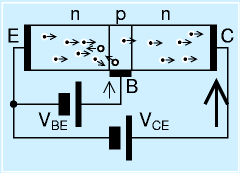 |
| B−E間はダイオードのように動作するものの、Bの電圧によってきて、Bに入った電子の大部分はそのままCに流れていく。 |
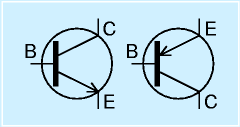 |
| 左、NPNトランジスタ、右:PNPトランジスタ。記号で区別がつくため、ふつうはBCEを書かない。矢印はエミッタにつけ、かつ電流の方向。外の○は書かないことも多いし、太線も太く書かないことが多い。形が重要。 |
トランジスタと名前がつくもの、おおむね増幅作用がある、足が3本以上の半導体部品ですが、ふつう、単にトランジスタといったばあいは、その元祖のバイポーラトランジスタをさします。
バイポーラトランジスタは図に示すように、pnp、npnと、3層サンドイッチ構造になっています。一見すると、先ほどのダイオードが2個逆向きに入っているようにも見えますし、実際、ある程度そのような性質も示します。この図では左右対称に見えますが、製造時には形状的、成分的なアンバランスを持たせて違う役目を持たせています。ここでは左をエミッタ、右をコレクタと呼んでおきます。真ん中の層はこの図に比べても圧倒的に薄くつくられ、ベースと呼ばれます。
その構造から、PNPトランジスタ、NPNトランジスタと呼ばれます。
ここでは、NPNトランジスタを例に、簡単に動作をみてみます。NPNトランジスタでは動作の主役がNにある電子となります。電子は電圧の低い方から高い方に流れます。(電子の流れと電流の向きが逆であることに注意)。
NPNトランジスタを使うときは、コレクタにエミッタより高い電圧をかけておきます。ただ、この状態では、そもそも、エミッタのN側からベースのP側にいくことができません。ここで、ベースにエミッタより少し高い電圧、順方向電圧降下分くらいをかけます。すると、ベースエミッタ間の壁を、電子がエミッタ側から越えられるようになります。
ベースとコレクタの間はダイオードとしてみると逆です。が、エミッタからベースに向かって来た電子はベースがあまりに狭く、勢いでコレクタの壁を超えてコレクタに入ってしまいます。コレクタに入ってしまえば、あとは単一な物質なのでコレクタ端子まで一直線です。
PNP型は電子の代わりにホールが主役になるだけで、同じような現象がおきます(ベース、コレクタにはエミッタより低い電圧)。
このように、トランジスタは、コレクタ−エミッタ間に電圧をかけておき、ベースにちょっとだけ電圧をかけると、コレクタエミッタ間にも電流が流れるようになる、という性質があります。これを電子部品としてみると、
- エミッタ電流IE=ベース電流IB+コレクタ電流IC
- コレクタ電流IC=電流増幅率hFE×ベース電流IB
- トランジスタ増幅動作時 ベースエミッタ電圧VBE=0.6〜0.7V(シリコン)
- トランジスタでスイッチ動作させる(=IB十分、ICそこそこ大)ときの最低限のVCE(VCEsat) ベースコレクタ電圧VCE=0.2V〜(トランジスタの作りに大きく依存)
となっています。コレクタ電流(エミッタ電流もですが)はベース電流に比例するという点が重要で、バイポーラトランジスタは電流増幅素子です。ただ、抵抗を使えば電圧は電流に、電流は電圧に直せるため、ちゃんと電圧増幅もできます。
この電流増幅率hFEは、ふつうのトランジスタで数十〜数百です。十分なようで足りないので、1個の部品に2段にトランジスタが入ったダーリントントランジスタという部品もあります(もちろん、2個のトランジスタでつくることもあります)。
MOS型トランジスタ(MOS-FET)
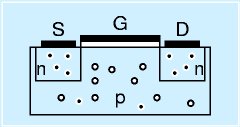 |
| MOS-FET模式図。Gはp部と接しておらず、ごく薄い絶縁膜(SiO2)がはさんである。 |
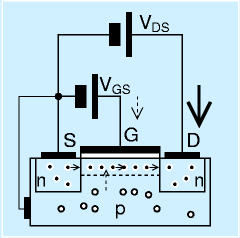 |
| Gに裏面より高い電圧をかけることで、わずかにある自由電子が寄ってくる。その結果、電子の通り道ができ、SとDで電流が流れるようになる。 |
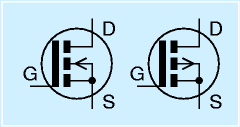 |
| 左、Nチャネル MOS-FET、右:Pチャネル MOS-FET。記号は実態に合わせて何通りかある。真ん中の端子が内部でつながっていれば、それがソース。もう一方がドレイン。NかPかは矢印の向き。 |
最近、集積回路ICの中身や、本講義の範囲のような、モータの制御をしたりする回路に急速に普及してきたトランジスタに、MOS−FET(Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor)があります。
これは同じトランジスタといっても、バイポーラトランジスタとはかなり構造が違います。
普段は図の右のようにnとnの間にpの空間があるため、電流は流れません。ここで、p領域と薄い絶縁膜で接するG:ゲート端子に電圧をかけます。すると、(いままで存在を無視してきた)p型の中にわずかながらある自由電子が電圧に引き寄せられて、nとnの間の領域に集まってきます。ある程度電子があつまると、あたかもn型と同じように振る舞い始めます。その結果、2個のn領域、D:ドレインと、S:ソース端子の間に電流が流れるようになります。
このトランジスタの特徴は、バイポーラのベースにあたる制御端子であるゲートは、「電圧をかけるだけ」で電流を流す必要がないことです(厳密には、電子を寄せる過程で電流が流れる)。ICはトランジスタの固まりのようなもので、バイポーラでつくるとベース電流だけでも馬鹿になりませんが、このMOS型をつかうとそれがいらなくなり省電力になります。また、モータなどを回すための回路にも、ディジタル回路の「電圧」だけを伝えればよく、心配事がへります。
- ゲートに電圧をかけることでソース・ドレインに電流が流れるようになる。
- 流れ始める電圧、流れやすさは種類さまざま
- 正の電圧をかけるnチャネル、負の電圧をかけるpチャネルがある。
- モータ制御につかうようなMOSFETはデジタル回路の電圧にちょうどよくつくってあったり、オン抵抗が小さかったり(=電流が良く流れる)するようにつくってある。
これら、2種類のトランジスタを以降では主に使っていきます。
以前は、MOS型が壊れやすいとか、遅いとかいわれたこともあり、バイポーラとMOSである程度用途が分かれていたこともありますが、半導体技術の進歩で、最近はかなりの部分がMOS型になってきています。また、ディジタル回路のところでふれた、TTLはバイポーラ型、C-MOSはMOS-FET型の回路になっています。
補遺:
そのほかのダイオード系素子:
ツェナーダイオード(逆向きに使うと一定電圧がでる<逆方向電圧がある程度になると電流が流れ出す)、ショットキバリアダイオード(PNではなく、一方が金属。順方向電圧降下が小さくなる)、ファーストリカバリダイオード(ダイオードは電圧によってすぐにオンオフするわけではなく、遅れがでる。それを小さくするように工夫したもの)、レーザダイオード(LEDの一種といえば一種。レーザがでる。レーザポインタや光通信)、フォトダイオード(LEDと逆に、PN接合に光を当てると電流が流れ出す。太陽電池もおなじ)、ブリッジダイオード/ダイオードブリッジ(整流回路用にもろにダイオードを組み合わせてパッケージにしただけ)
そのほかのトランジスタ系素子:
接合型FET(構造、製法が違う)、サイリスタ(NPNとPNPを一体にしたような形で一度オンすると流れっぱなしになる。電力回路用)、トライアック(サイリスタを双方向に接続して双方向に電流が流せるように。交流電力回路用)、GTOサイリスタ(オフにできるようにしたサイリスタ)、IGBT(FETとバイポーラのハイブリッドダーリントン接続。入力はMOS-FETっぽく、電力制御はバイポーラで。大電力用)、フォトトランジスタ(フォトダイオードをトランジスタのベースに接続)
ダイオード・トランジスタを含む回路
これまで扱ってきた回路は主に、抵抗のみ(時々コンデンサ)が、電圧や電流の計算に関与していました。これらは、基本的にオームの法則に従うため(広い意味でコンデンサも)、単純な計算ですみましたが、ダイオードやトランジスタは電圧−電流の関係が非線型(非直線的)で多少複雑になります。
これからさきは良く扱う回路ですので、例をあげてその計算法を学びます。
ダイオードを含む回路の解析
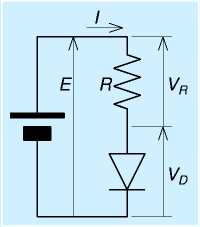 |
| 抵抗とダイオードを直列接続した回路の例。 |
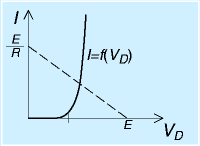 |
| ダイオードの電圧−電流特性 |
ダイオードを含む回路の電圧や電流の解析を行います。
ここではもっとも単純な例として、直列接続を行います。
ダイオードの特徴は、
- ある閾値電圧(シリコンでは0.6〜0.7V)を越えるまでは電流が流れず、それを越えると急に電流が流れるようになる。
- 逆に言えば、電流が流れているときは、端子間に常にほぼ一定の順方向電圧降下が生じている。
です。そのことを念頭に置けば、簡単に計算できます。
簡易な計算方法:
右図において、
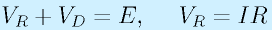
は自明です。ここで、ダイオードの電圧をVD=0.7[V]と決めつけます。すると、単純に
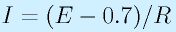
もしくは
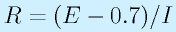
となります。
一般的なダイオードの場合、流れる電流を意識することはあまり多くありませんが、LEDを点灯させるときは、その電流を決めるため(電流で明るさが決まる、壊れる)に同様な計算を行います。
例)
ふつうのLED: VD=2[V]程度
電源:ディジタル回路でありがちな E=5[V]
設計電流:I=10[mA] (まあまあ流す方)
の場合、
R=(5-2)/0.01=300[Ω]
この場合、電源が2[V]に下がるまでは、減少していきますが電流が流れ=光り続け、下回ると光らなくなります。電球はフィラメントの抵抗の発熱による光なので、電圧がさがっても色が赤っぽく(温度が下がる)なりながらも、かすかには光ります。
詳細な計算方法:
ダイオードは厳密には右図のグラフのように、閾値電圧を超えたところからカーブを描いて(指数的に)電流が増えます。ちなみに、常に「VD=0.7」という仮定はこの線が垂直に立ち上がることを意味します(電流にかかわらず電圧一定、なので)。
このカーブは、ダイオードの作り方によるため、ダイオードのデータシート(性能表)にグラフが出ています。
ここでは、ダイオードの特性を
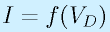
とおいてみます。
この場合、
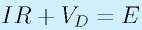 より
より
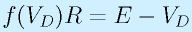 と変形され
と変形され
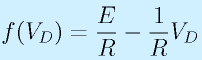 となります。
となります。
ここで、左辺は、もとのダイオードの関数、右辺は図の破線で書いた直線になります(VD=0, 右辺=0の点を考えればグラフは書ける)。この等式が成り立つのは、線の交点です。
つまり、ダイオードと抵抗の回路で厳密に電流がどれだけかを計算したければ、回路の式をf(V_D)=の形で解くことで破線で表したようなグラフを得て、データシートのグラフに重ねてみれば良いことになります。もしくは、ダイオードの特性そのものをある曲線近似して、その式を元に解きます(回路シミュレーションは一般に後者)。
以上のように計算することができます。
バイポーラトランジスタを含む回路の解析
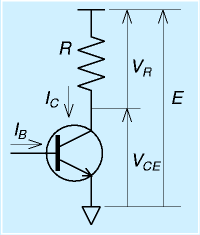 |
| 抵抗とトランジスタによる回路1(エミッタ抵抗なし) |
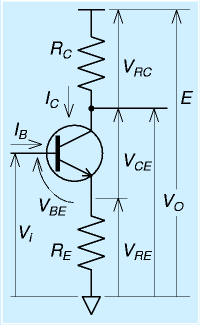 |
| 抵抗とトランジスタによる回路2(エミッタ抵抗あり) |
つぎに、トランジスタを含む回路について考えます。
トランジスタの特徴は、
- ベース電流IBをhFE倍するとコレクタ電流ICとなる。
- ベースエミッタ間はダイオードと見なすことができる=ダイオードを含む回路と同じに考える。
です。これらを別個に考えていけば、それほど難しくはありません。
例1:トランジスタと抵抗1本
回路に関わる式を書き出します。
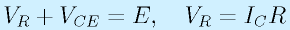
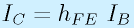
これを単純に変形して、
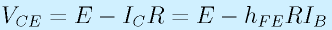
となります。I_Bの増減で、V_CEが減増します。ただし、当然ですが、V_CEがマイナスになることはありません。
また、ある程度はV_CEがないとI_Cが流れないため、トランジスタにもよりますが、下がっても、V_CEは0.2〜0.3[V]程度と考えておきます(データシート等をみるとV_CE(sat)などと表記)。モータ制御などで大電流を流すほど、一般には高めです。ちなみに、V_CEが足りなくなると、I_BやhFEに関係なくI_Cが下がるため、結果的にV_CEが上がって適当なところで落ち着きます。
例2:トランジスタと抵抗2本
同じく、回路に関わる式を書き出します。
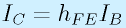
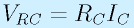
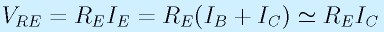
ここで、ベース電流IBはコレクタ電流ICより小さいため、無視しています。
また、この式の組み合わせにより、
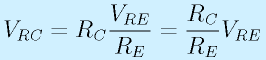
が成立します。
さて、ベースに電圧Viを入力します。このとき、
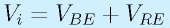
ですが、ベース・エミッタ間はダイオードと似たものであり、実際、動作時にはダイオードと同じように順方向電圧降下が生じています。さらに、その値はおおむね、0.7[V]です。そのまま値を入れると、
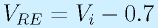
よって、出力電圧Voは
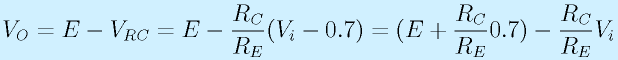
で得られることになります。これは、Viが1[V]増えると、Voが(RC/RE)[V]減ることになります。
よって、オフセットはついていますが、反転増幅回路のような電圧増幅ができ、その増幅率がRC, REで決められます。
もちろん、トランジスタが動作する範囲でしか動作しないこと、増幅率は近似の問題が無い範囲で数倍にとどまることなどの制約はあります。
ちなみに、何かの拍子にICが少し増えたとすると、VREが上がります。その結果、VBEが目減りし、IBが減ります。結果的にICが減ることになります。つまり、回路として、なにかの拍子にずれても元に戻る方向に動作します。これはオペアンプの増幅のときもあった、回路の安定性です。
以上のように、トランジスタをつかうと、増幅回路を作ることができます。バイポーラトランジスタについては、品種が変わってもほぼ上記の計算が成り立ちます。MOS-FETについては、素子の特性の影響を受ける部分が多く、一般論としては説明しませんが、電圧で電流を制御する、という動作になります。
補足:
今回の回路はコレクタから線を取り出しています。エミッタから線を取り出した場合、V_RE=V_i-V_BEとなり、つねに、入力電圧(からV_BEさがったところ)を追随する信号が得られます。これをエミッタフォロワといい、ある信号の電流だけ増強する(後ろに電流を取られても影響を受けにくくする)場合に使われることがあります。
このページここで終了。
熊谷正朗
[→連絡]
東北学院大学
工学部
機械知能工学科
RDE
[| ]
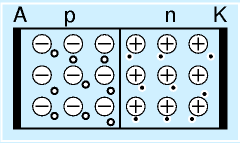
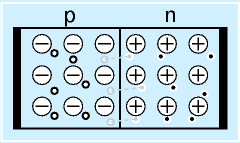
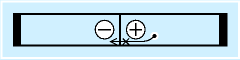
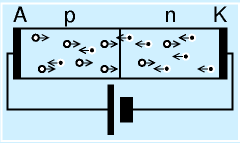
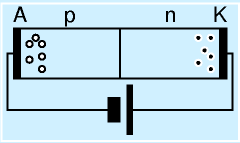
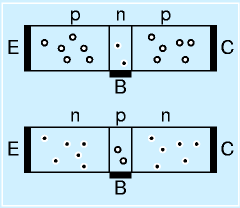
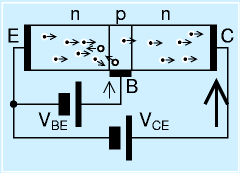
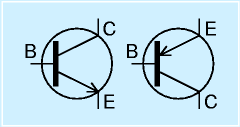
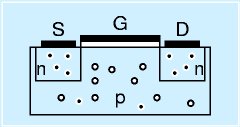
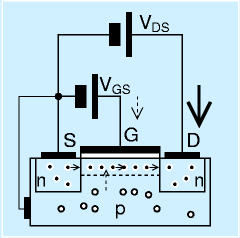
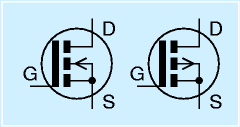
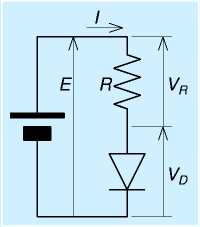
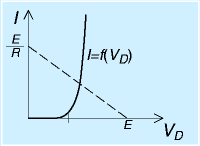
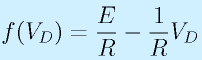 となります。
となります。