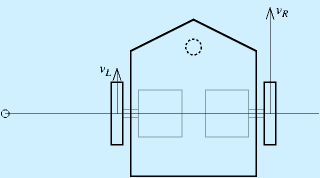
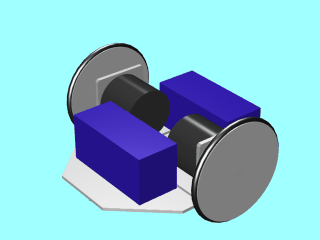
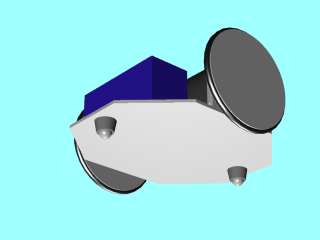
ここでは移動ロボットの大部分が採用している移動機構である車輪について、扱います。
最近はちらほらと脚移動が見えるようになってきましたが、依然として移動ロボットの大部分は車輪移動であり、平坦地での移動に限れば今後も脚にとってかわられることはないと考えられます。
車輪移動の場合、最低限2個のモータの回転を制御すれば平面を自由に走り回ることができ、また停止しているときに必要なエネルギーは斜面でなければ微々たるものです。
制御回路をちょっと工夫すれば、減速時に走行の運動エネルギーのある程度を電気エネルギーとして回収することも可能であるなど、効率にも優れます。
ところが、特殊な例を除いて、車輪移動は移動方向に大きな制限があります。
自動車や自転車は前後には走りますし、カーブして走行もできますが、真横には移動できません。
そのため、真横に移動するには切返などが必要です。
これは制御上もやっかいな問題になり得ます。
そのようなわけで、移動ロボットの代表例として、車輪移動の基礎を学びます。
車輪による移動には様々な利点がありますが、その一つにはそこそこの範囲をそこそこ正確に移動できる、もしくは移動した経路をそこそこ正確に算出できるというものがあり、このページでも後にその方法について扱います。 その際に大きな前提となることが「車輪が滑らない」ということです。車輪移動ロボットの数学は、この前提の上に成り立っています。 つまりドリフト走行は禁止です。以下では、車輪が滑らないことを前提にします。
車輪による移動は、ロボットを支えている車輪が適当に転がることによって行われます(当然?)。 ここで重要なことはすべての車輪が「滑らない」という条件です。 車輪が滑らないという前提では次のようなことが言えます。
以下では単純で代表的な2種類のロボット形態を示します。
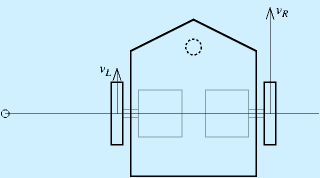 |
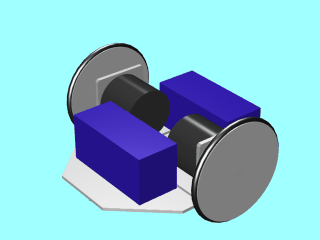 |
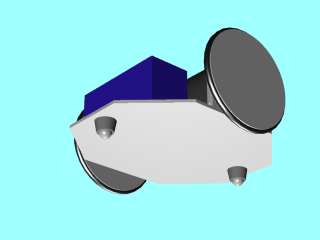 |
この方式が広く使われているのは、
ロボットの制御は両輪の回転で行います。
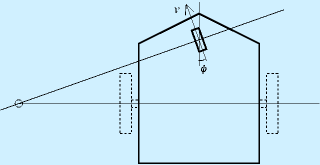 |
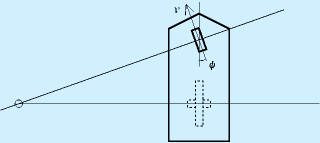 |
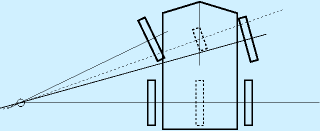 |
右の図で一番上は、基本的な構成です。後輪2輪は車体を支えるためだけに自由に回るように取り付け、前輪の方向(ψ)を決めて、車輪を回転させて移動します。ただし、この場合、駆動機構をコンパクトに納めるのがたいへんなので、前輪の回転は自由に、後輪の一方を駆動輪にする場合もあります。
駆動のアンバランスを避けるためには、ディファレンシャルギアを搭載して両輪を駆動しますが、移動ロボットでそこまでやることはあまりみられません。
旋回中心は後輪の軸と前輪の軸が交わったところにできます。
二つ目は2輪にしてしまった構成です。数学的には、3輪と解釈されるよりも、この2輪モデルがよく使われるようです。
三つ目の図はよくある自動車の構成です。4輪にして前輪2個に操舵機構を設けます。
ここで注意することは、すべての車輪の軸が旋回中心で交わるために、前輪の操舵角が左右で異なることです。
内側の車輪がよりきつく曲がります。こうしないと滑りが発生するわけです。
そのため、自動車の場合は特殊なリンク機構(アッカーマンステアリング機構)などでこの関係が成り立つようにします。
また、向きは同じですが、この状態では後輪は左右で回転数が異なります。
内側に比べて外側の車輪が多く回転する必要があります。
ロボットならモータを独立につけることもありますが、自動車の場合にはエンジンは一個なので(電気自動車は別)、ディファレンシャルギア(デフ)でその回転数差を作り出します。デフは「入力の角速度×2=右の角速度+左の角速度」となる機構で、平均速度はそのままに差を作り出します。
もちろん、前輪駆動の場合も左右に回転数差があるので、デフは必要です
(蛇足:4輪駆動だと、前後各々の平均の間にも差があるので前後間にセンターデフが必要)
この節ではロボットのモデルを数学的に解釈します。 上で大きく2種類のロボットがあるとしましたが、ここでは扱いやすい対向2輪型を解析します。
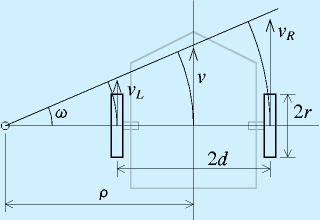 |
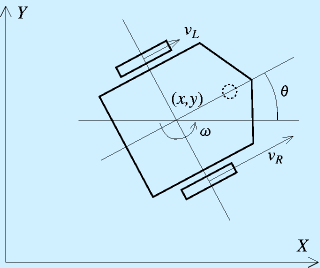 |
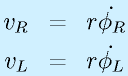
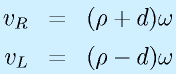
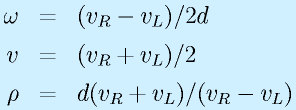
ロボットを外部の座標系で見た場合は
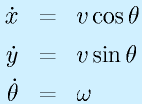
となり、ロボットの運動が両輪の回転角速度をもとに記述できることが確認できました。
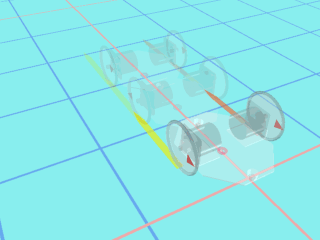 |
 |
一つ目の例では両輪を同じ速度で加減速させています。
両輪に速度差がないので、真っ直ぐに走ります(旋回半径は無限大)。
二つ目の例では左右に一定の比率の速度差をつけています。
具体的には、右は左の約3倍(10:3)の速度です(後半は逆に1:2)。
上の回転半径の式より、d(10+3)/(10-3)でだいたい2dくらいになります。
また、速度比が一定なので、中心位置は変わりません。
映像だけの三つ目では、より複雑に車輪を加減速しています。
旋回半径が伸び縮みすることが見えますし、左右が逆回転する際には両輪の間に入っています。
このように小回りや複雑な運動をしやすいことが対向2輪型の特徴です。
参考:
映像のパラメータ
| 車輪径(2r) | 100mm |
| 車輪間隔(2d) | 190mm |
| 数値解析間隔 | 1/30秒 |
| 床面格子間隔 | 200mm |
直線走行、ワールド系、320x240 (2018/04/17, 224,725 bytes)
直線走行、ロボット追跡系、320x240 (2018/04/17, 304,725 bytes)
円弧走行、ワールド系、320x240 (2018/04/17, 285,525 bytes)
円弧走行、ロボット追跡系、320x240 (2018/04/17, 439,125 bytes)
複合走行、ワールド系、320x240 (2018/04/17, 304,725 bytes)
複合走行、ワールド系、640x480 (2018/04/17, 1,251,925 bytes)
複合走行、ロボット追跡系、320x240 (2018/04/17, 439,125 bytes)
※ワールド系:カメラをワールド座標に固定。ロボット追跡系:ロボットの位置を基準に移動カメラを設置、ただしカメラの姿勢は固定。
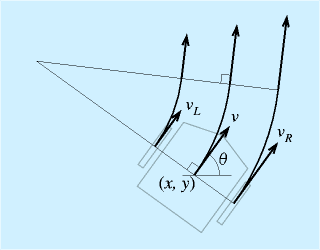 |
| (a) 車両の移動 |
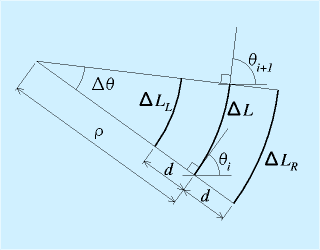 |
| (b) 円弧に近似 |
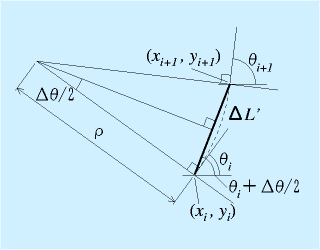 |
| (c) 座標の移動 |
車両の運動は上述の通り、
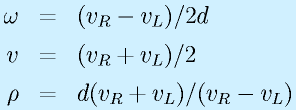
および
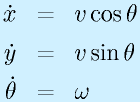
で表されます。
これを積分すれば x,y,θが得られますが、実在のロボットでは積分はできません。
積分は微少時間を扱うことが前提です。
またロボットを制御するプログラムは一般に一定の時間間隔で車輪の回転センサなどの情報を読み取り、モータを制御します。
CPUは複数のことを同時にはできないため、入力→演算→出力という処理を繰り返すためです。
そこで、積分する代わりに、この制御の1サイクルの時間Δtの間の運動を考えます。
なお、このΔtを制御周期と呼びます。またそのΔtの間の処理区間そのものも制御周期と呼ぶことがあります
時間Δtの間の移動を右図に示します。
左右の車輪の周速度をvL, vRとし、ロボット中心の移動速度をvとします。これら関係は上の通りです。
次に、図(b)に示すように、時間Δtで左右の車輪およびロボット中心がそれぞれΔLL、ΔLR、ΔL 移動したとします。
![]()
または、車輪の回転角度に対して、
![]()
一般に、車輪につけるセンサは速度センサではなく、角度センサであるため、このΔLL、ΔLRはある制御周期で読み込んだ車輪の回転と、次に読み込んだ回転の差として得られます。
またこのΔtの間、速度は変化しないものとし、ロボットは一定の半径ρの円弧運動を行うとします。
Δtで旋回中心のまわりにΔθだけ回転したとすると、
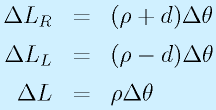
なので、
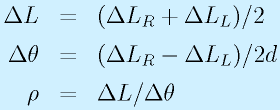
となります。
次に移動量を算出します。ロボットの位置、姿勢を制御周期iのときに xi,yi,θi、次の周期でxi+1, yi+1, θi+1 と表記します。
まず、角度については、
![]()
です。位置については、Δθが十分に小さい場合は、
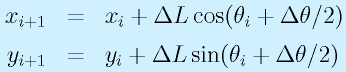
とかけます。
Δθ/2 を加えるのは、移動の前後のロボット角度の平均です。
それに対して、Δθ(の絶対値)がある程度大きいときは、右図(c)のΔL'をまじめに計算します。
始点終点と旋回中心でできる三角を半分にして考えると、
![]()
となります。これで、
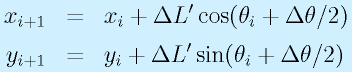
と計算すれば、「Δtの間、円弧運動をしている」という仮定に対しては正確な演算結果が得られます。
なお、ここで注意すべき点は後者ではρが必要な点です。
もし、Δtの間に左右の車輪がすっかり同じ角度回転した場合、ρが無限大になります。
ソフトウエア上ではΔθ=0で割るため、大抵のシステムでは「0で割りました」エラーがでます。
そのため、ΔLL=ΔLRの場合は、ΔL'=ΔLと別扱いにする必要があります
(演算精度を考えると、Δθがある程度小さくなったら切り替える必要あり)。
以上の演算を時々刻々と重ねていけば、ロボットの車輪の回転角度を測定すれば、ロボットの位置と姿勢を得ることができます。 この手法をデッドレコニングと呼びます(オドメトリなど他表記あり)。
※このページの映像は、車輪の左右の回転を決めて、本手法で位置を算出しています。
表計算ソフト(OpenOffice)上で時系列で生成した座標をCGモデルに反映させて映像化しています。
ここでは車輪移動ロボットの制御のうち、代表的な「経路に沿って走行」という手法を紹介します。
上述の対向2輪型ロボットは両輪の回転を制御することで様々な運動ができます。 その中で、人間が直接操縦するのではなく、自律的な用途のうちで、主なものを考えると
ロボットを走行させる場合には、いくつかの方法があります。
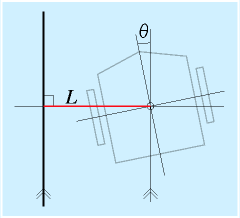 コンピュータの中に仮想的なラインを設定して、自己位置推定で得たロボットの位置と姿勢角度を仮想的なラインと比較し、ロボットを目標軌道に載せる方法です。
コンピュータの中に仮想的なラインを設定して、自己位置推定で得たロボットの位置と姿勢角度を仮想的なラインと比較し、ロボットを目標軌道に載せる方法です。
この方法でも非常に多くの手法が提案されていますが、主に考慮されることは以下の二つです。
例をあげます。
右図に示すように、ロボットの中心から軌道までの距離をL、軌道の接線方向とロボットの進行方向の成す角をθとします。
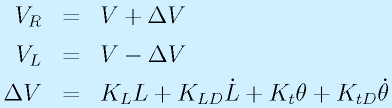
ここでK?は定数で、適宜設定します。
V は平均移動速度で、両輪の速度差ΔVでロボットの旋回成分を操作して走行します。
KLおよびKtの項はLとθがゼロになるようにするためのものです。
Lがゼロでないときは、ロボットの進行方向を線の向きに向ける必要があります。
KLDおよびKtDの項はLとθの速度を制御します。
例えば、ロボットが線に近づいてLが十分小さくなってきたとしても、ロボットが勢い良く線に近づいている場合(つまりθが大きいわけですが)にロボットの進行方向を変える必要があります。
パラメータが4つあって決めるのに困りそうですが、実はやってみると案外後半のθの項がなくてもそこそこ動くようです。
KLDとKtが似た性質を持っていることもあると考えられます。
また、極端にはKL以外が0でも使えることがあります。ただしこの場合は線を挟んでロボットが左右に蛇行することになり、スムーズに走らせるには微分項も含める必要があります。
この方法の難点は軌道の定義方法です。直線や円弧のような軌道であれば、Lを求めることは容易なのですが、複雑な軌道を作ろうとすると、どこが最近点なのかを求めることが難しくなります。
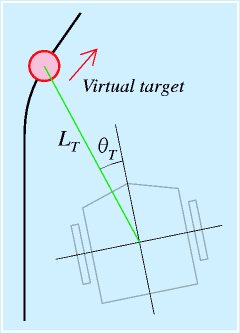 上の方法の問題点は軌道とロボットの位置関係を求めることがやっかいなことです。
その一つの解決案として、目標軌道の上で仮想的な(実質的な)ターゲットを目標速度で移動させ、ロボットはそれに追従するように仕向ける方法が考えられます。
上の方法の問題点は軌道とロボットの位置関係を求めることがやっかいなことです。
その一つの解決案として、目標軌道の上で仮想的な(実質的な)ターゲットを目標速度で移動させ、ロボットはそれに追従するように仕向ける方法が考えられます。
まず、自己位置推定で得たロボットの位置と姿勢をもとに、移動する仮想ターゲットの位置をロボットの座標系上に変換します。
すると、ロボットから見て、ターゲットの位置を距離LTと方向θTで表せます。
これを元に、例えば
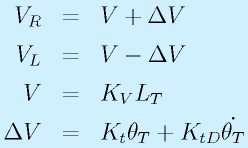
とします。
この式の意味するところは、「平均的な車両速度はターゲットとの距離に比例」「車両の方向がターゲットの方向を向くように姿勢を回転させる」です。
ロボットの頭にゴム紐をつけて引っ張るようなイメージです。
この方法はターゲットさえ移動させればいいので、かなり扱いやすい方法です。
また、ターゲットは仮想的なものである必要はないので、目標追尾型の動作にそのまま使えます。
ただし、原理的にはロボットがターゲットにたどり着くことはないので(そのまえにLTが小さくなることで速度が小さくなってしまう)、目標地点までターゲットを動かしただけでは目標にたどり着けないという問題点があります。
また、KV, Kt, KtDの各係数を大きくしすぎると制御が発散しかねませんが、小さくするとターゲットとロボットの間にすきまが開くため(よわいゴムひもで引っ張る感じ)、細かな経路計画をしてもおおざっぱにしかついてきません。
その結果、回りにぶつけたりすることがあり得ます。
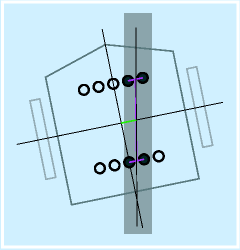 普通にライントレースロボットといったら、このタイプです。
路面にひかれたラインをセンサで読み取り、そのラインをたどるように走ります。
ラインは白い床に黒い線といった明暗で示す場合、金属箔のテープをはったり磁石を埋めたりする磁気的に示す場合などがあります。
普通にライントレースロボットといったら、このタイプです。
路面にひかれたラインをセンサで読み取り、そのラインをたどるように走ります。
ラインは白い床に黒い線といった明暗で示す場合、金属箔のテープをはったり磁石を埋めたりする磁気的に示す場合などがあります。
一番原始的には、ロボットの軸に対称に、左右にセンサを取り付け、左のセンサが反応したら右に進路変更、右のセンサが反応したら左に進路変更、という方法があります。 これはライントレースのキットやおもちゃでも使われるような方法で、このくらい単純でもそれなりに動作します。ただし、ロボットは頭を激しくふりながら前進します。
ふれを小さくするにはセンサの間隔をつめることが解決策の一つです。
ただ、その場合はラインからはずれる確率も高くなるので、センサの数も増やします。
また、センサの間隔をラインの幅よりも狭めることで、複数のセンサでラインを読むようにして、読みとばしを避けると同時に、センサの出力を平均化することでセンサの数以上の細かさを得ることができます。
例えば、右の図で前方のセンサは右二つが線を踏んでいます。
5個のセンサにそれぞれ重みとして 2,1,0,-1,-2 を割り当てると、(-1*1-2*1)/(1+1)=-1.5 と計算できます。
2〜-2でセンサの数は5個ですが、1個か2個同時に踏む程度の間隔を設定すると、9段階の位置になります。
センサをオンオフだけではなく、アナログ的に処理するとさらに分解能をあげられます。
ふれを小さくするもう一つの方法はロボットの姿勢を反映することです。
最初に述べた方法のように、ロボットの姿勢をフィードバックします。
センサの数をけちる場合は、センサで読んだラインの位置の時間変化をフィードバックします(KLDに相当)。
センサを前後に並べることができる場合は、右図のように前後のセンサ群で検出したラインの位置から線の傾きを出し、それを反映させます(Kt項に相当)。
センサを倍つけなければならないようですが、このラインセンサによる方式ではセンサ群は車軸より前方にないとやっかいという性質があります(車軸から遠いほどなめらかに動く:原理を考えてみましょう)。
そのため、ロボットをバックさせるときは、後ろにもセンサがあったほうがいいわけです。
すると、車両の傾きを得るにも使えることになります。
この方法は工場での搬送車などに良く使われます。物理的なラインが存在するため、車輪の滑りなどにも強く、単純な制御方式(=信頼性を確保しやすい)で移動できるためです。
また、ラインセンサを流用すると停止線を読んだり、地面のバーコードを読み取って動作を変えたり様々な使い方ができます。
そのほか、高速道路での自動運転の研究でも、道路に磁石を埋めてそれを磁気センサで読み取る方式が進められています。
自動運転というとカメラを搭載して画像処理という方法がありがちですが、磁気センサの方が単純であるため、信頼性を確保しやすいといえます。
しかし、あまりに単純にこの方法をつかうと、センサの数が十分でないと動きががたがたしたり、精度が確保できなかったり、上二つの方法に比べて見た目は劣ります。
そこで、基本的には自己位置推定をベースに走行して、ラインを読みながらその補正を行う、という合成手法が使用される場合もあります。
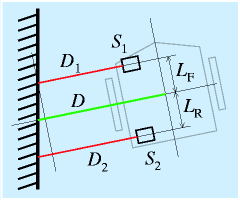 物理的な対象をたどるばあい、壁を伝うというケースもあります。
この場合、壁までの距離を測るセンサが必要になります。
ポピュラーなセンサとしては、超音波と光三角測量のセンサがあります。
物理的な対象をたどるばあい、壁を伝うというケースもあります。
この場合、壁までの距離を測るセンサが必要になります。
ポピュラーなセンサとしては、超音波と光三角測量のセンサがあります。
超音波センサは、超音波を飛ばしてから返ってくるまでの距離を測ります。
相手が音を反射する材質ならなんでもいいのですが、雑音、最悪の場合はロボット自身のギアの出す音でも誤動作する場合があり、比較的静かな環境で使う必要があります。
最近使いやすくなった方法に光を用いて三角測量を行うセンサがあります。
通称、PSDと呼ばれていますが、小型のセンサで、電源をつなぐだけで数十センチまでの距離をそれに対応する電圧で出力してくれます。
値段も含めて非常にお手軽なセンサですが、赤外線を使うため、赤外線が反射しにくい素材ではつかえません。
※ PSDは本来はそのセンサに使われている受光素子の名前
さて、距離が測れるセンサがあったとして、ロボットの側面に、前部と後部に一個ずつつけます。
一般には左右にそれぞれつけるので、4個になりますが、図では左側面だけ描きました。
このセンサで壁までの距離 D1、D2を測定します。
なお、光のセンサの場合は図に示すように真っ直ぐ測れますが、超音波の場合には広がりがでるので、真っ直ぐは測れません。
ただ、結果に悪影響をだすようなずれはあまりでません。
このとき、これまで同様に考えると、
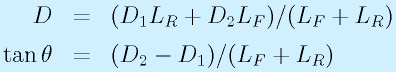
というように、壁までのロボットの距離と、壁との傾きがわかります。
一般には、Dが目的の距離D0になるように、(D-D0)がゼロになるように制御します。
この方法は壁までの距離を測ることができればよく、壁への衝突回避能力もついてくるのでお手軽です。ただし、壁がなめらかなところなら問題ないのですが、日本の一般的建築のように、壁がぼこぼこに入り組んでいる場合は距離が頻繁に変わって制御に失敗しやすくなります。
紹介した4つの方法のうち、上二つは軌道を数式として事前に持っていることが前提です。
ロボットの軌道を計画する場合は、多くの場合はパラメトリックな線を使います。
例えば、円を表す場合、
![]()
という書き方の他に
![]()
という書き方があります。
後者がパラメトリックな書き方で、媒介変数:パラメータであるtを変化させることで線ができます。
上で例示した仮想的なターゲットを一定速度で円弧上を動かすという場合は、後者の式でtを一定速度で変化させれば一発です。
それに対して、前者はそう簡単にはいきません。もちろん、yをxの関数で表す式を使うこともありますが、これは経路が基本的に真っ直ぐで、ちょっと脇にそれる程度の場合しかつかえません。
軌道を作る場合の数式も出るにもいくつかあります。
以上のような式を用いて、始点から終点まで障害物を避けるような軌道を立案して、その線に沿って、自己位置推定をしながら走るようにすれば、ロボットはかなりいろいろな仕事が出来るようになります。
移動できるようになると、障害物を知るためのセンシングが重要になってきます。
それはまた次の機会に。