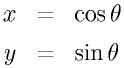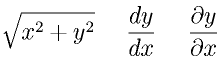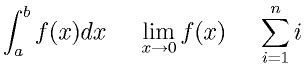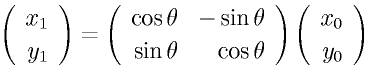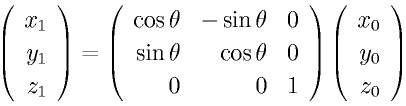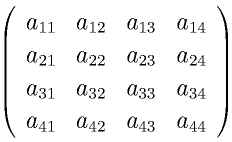数式画像生成 eqn2gif オンライン版手引き
最終更新: 2011/02/10 19:52:39
[| ]
最終更新: 2011/02/10 19:52:39
eqn2gif オンライン版
ps2img のうち、需要のありそうな eqn2gif のオンライン版を作成しました。
LaTeX形式の数式をかければ、簡単に数式画像が得られます。
- LaTeX形式(eqnarray)で記述した数式を画像(gif)ファイルに変換します。
- 出力画像の解像度は倍率指定で設定できます。
1倍:おそらく、10ptフォント、72dpi 相当
画像サイズではなく倍率なので簡単な数式も複雑な数式も、同じ文字サイズで出力されます。
すべて同じ縮小率で張り込めばきれいなスライドがつくれます。
- 画像出力時にスムージングが可能です。
WEBページの執筆など、原寸で、ディスプレイ上で見せる場合はスムージングを使用し、印刷用原稿に貼り込む場合はスムージングせずに倍率を大きくして変換することをおすすめします。
スムージングした画像と、スムージングなしで縦横2倍の画像は、ファイルサイズはほぼ等しく、PowerPointなどは適宜表示の際にスムージングしてくれるので見た目はかわりません。しかし、印刷するときはスムージングにより発生した中間色部分が、レーザプリンタなどではカビが生えたようになります。
セキュリティを考慮して、TeXのコマンドは使用を制限していますが、大抵の数式を作るにはたぶん足りると思います。
試してみて、常用するほど便利でしたら、ps2imgを手元にインストールしてご使用下さい。
使い方
使い方:
- [数式入力]枠に数式をLaTeX形式で入力して、[変換]ボタンを押します。
正常に変換できれば、ボタンの下に画像が表示されます。
- 出力倍率は1〜10の整数値を入れてください。
- [変換(アンチエイリアス)]を押すとスムージングされます。
- [処理メッセージ]には変換処理の報告がでます。
文法に誤りがあると、LaTeXのエラーがでます。
間違ったところが示されるので、なんとなくわかるとおもいます。
使用できないTeXコマンドやコマンドを打ち間違うと[使用できない]表示が出て、それを除外した部分の数式が変換されます。
- 使用可能なコマンド(含むギリシャ文字)は[使えるコマンド一覧]を押すと処理メッセージ欄に表示されます。
使用例1:一般
y=f(x)

x=(\sin\theta_0)^2, ~~~~ y=x^{12}
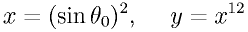
下つきは"_"、上付きは"^"、文字が複数の時は"{}"で囲む。
"~"を入れると適宜すきまが空く。
ちなみに、ただ"sin"と書くと文字がイタリックになって芳しくない。sinやcosはローマン体でかく。
\alpha \beta \gamma \delta \epsilon \zeta \eta \theta \iota \kappa \lambda \mu
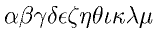
\nu \xi \o \pi \rho \sigma \tau \upsilon \phi \chi \psi \omega
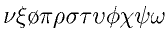
A B \Gamma \Delta E Z H \Theta I K \Lambda M
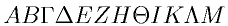
N \Xi O \Pi P \Sigma T \Upsilon \Phi X \Psi \Omega

\varepsilon \vartheta \varpi \varrho \varsigma

ギリシア文字は全角でも出せないことはないけど、これらを使った方がきれい。
大文字は普通のアルファベットと同形のものがあることに注意。
\left( \begin{array}{rr} a & b \\ c & d \end{array} \right)

\left[ \begin{array}{r|r} a & b \\\hline c & d \end{array} \right]
![\left[ \begin{array}{r|r} a & b \\\hline c & d \end{array} \right]](eqn/eqn2gif_online.bhtml.eqn109.gif)
行列の書き方。"{array}{rr}"の"r"の数が列の数、"\\"の数が行の数になる。"|"を入れたところに縦線が、"\\\hline"とすると横線が入る。
x&=&\cos\theta \nonumber\\ y&=&\sin\theta
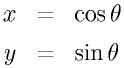
"\nonumber\\"をいれると改行する。そのとき"&?&"と囲んだ部分がそろうようにレイアウトされる。
\dot{x} ~~~~ \ddot{x} ~~~~ A \ldots B ~~~~ A \cdots B ~~ \pm ~~ \mp
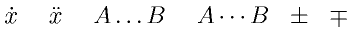
\sqrt{x^2+y^2} ~~~~ \frac{dy}{dx} ~~~~ \frac{\partial y}{\partial x}
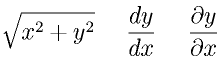
\int_a^b f(x)dx ~~~~ \lim_{x \rightarrow 0} f(x) ~~~~ \sum_{i=1}^n i
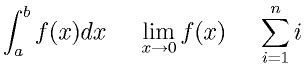
使いそうな記号。"\partial"のあとの空白は重要。"\int"などは "_" "^"の動作が変わることに注意。
そのほか、各種記号などは LaTeXコマンドシート一覧の8、9、11の項目を参照。ここの一覧のうち、そこそこ使えるようにしてあります。
使用例2:定義済マクロ
\vect{C}=\vect{A}\vect{B} \neq \vect{B}\vect{A}
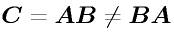
"\vect{}"でボールドイタリック(行列、ベクトル)表記。
\Vt{x_1}{y_1}=\Mtt{\cos\theta}{-\sin\theta}{\sin\theta}{\cos\theta}\Vt{x_0}{y_0}
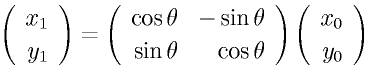
"\Vt{}{}", "\Mtt{}{}{}{}" で2要素列ベクトル、2×2行列。
\Vs{x_1}{y_1}{z_1}=\Mss{\cos\theta}{-\sin\theta}{0}{\sin\theta}{\cos\theta}{0}{0}{0}{1}\Vs{x_0}{y_0}{z_0}
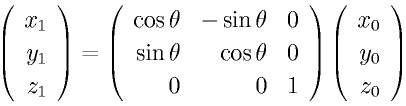
"\Vs{}{}{}", "\Mss{}{}{}{}{}{}{}{}{}"(9個必須) で3要素列ベクトル、3×3行列。
\Mqqa{a_{11}}{a_{12}}{a_{13}}{a_{14}}{a_{21}}{a_{22}}{a_{23}}{a_{24}}\Mqqb{a_{31}}{a_{32}}{a_{33}}{a_{34}}{a_{41}}{a_{42}}{a_{43}}{a_{44}}
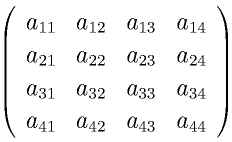
"Mqqa" と "Mqqb" は必ずセットで使用し8個ずつ引数を渡して、4×4の行列。"Vq{}{}{}{}"もある。
\cth, \sth, \Cth, \Sth, \cph, \sal, \Cps, \cth_1
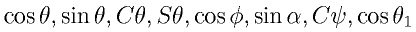
良く使いそうなものを短縮。最後のように、そのあとに添字がつけられる。
熊谷正朗
[→連絡]
東北学院大学
工学部
機械知能工学科
RDE
[| ]

![\left[ \begin{array}{r|r} a & b \\\hline c & d \end{array} \right]](eqn/eqn2gif_online.bhtml.eqn109.gif)