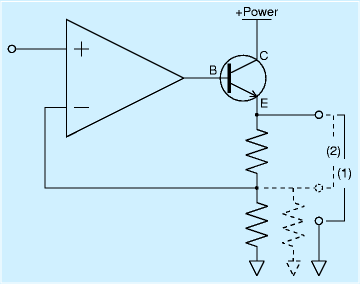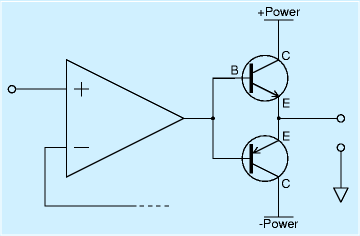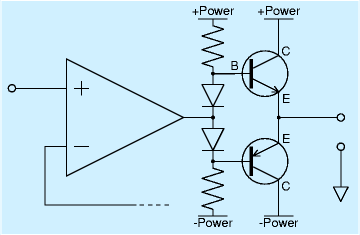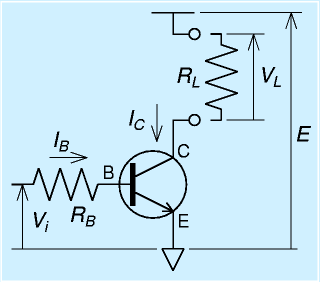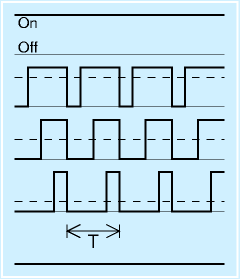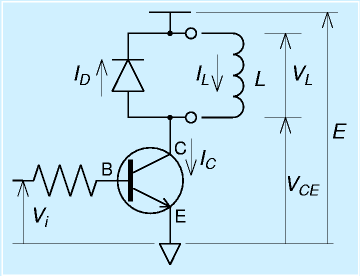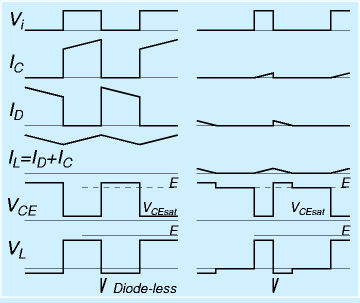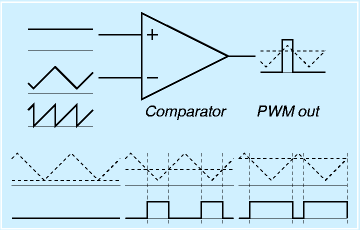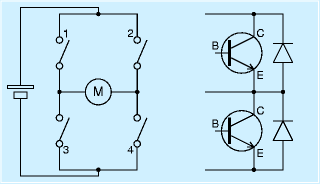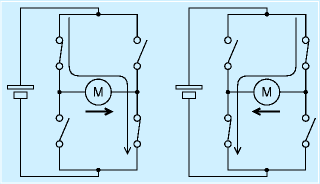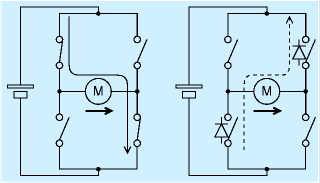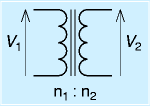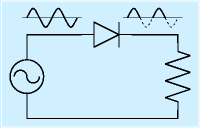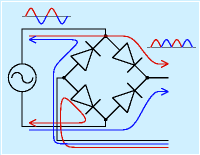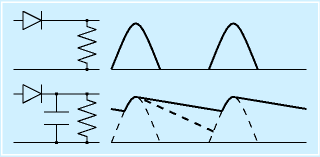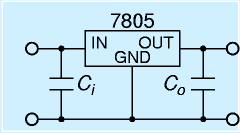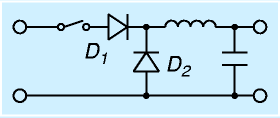ここでは、電気を動きに変える働きのアクチュエータと、その駆動方法について扱っていきます。
電気の使い方を考えるとき、大きく2種類に分けることができます。
一つは信号としての電気であり、ここまで扱ってきた内容の大半のベースとなる考え方です。
この場合、電流はそれほど大きくなく、それゆえ、電圧の(小さな範囲での)大小、電流の(小さな範囲での)大小を考えていました。基本的に、「紙の上に書いた回路図通り」つくることで、細かな性能は別として、目的をかなえることができ、電圧や電流が大きすぎて部品が発熱したり、壊れたりということはありません。
もう一つの使い方はエネルギーとしての電気です。モータを回したり、照明をつけたりと、電気を「別のエネルギーに転換して使うこと」と目的とした電気です。信号として扱う電気は信号が伝わることが最低限必要な量であるのに対して、こちらは少なくとも、その「他のエネルギー」に転換する分は必要です。その上、変換効率は100%ではないため、それ以上の量を必要とするのが一般です。
それゆえ、明らかに「大きな電気」を操作する必要があります。
最終的に他の形態にする電気も、取り扱う過程で若干〜多大に損失(無駄)が発生します。
他のエネルギー同様、損失は最終的に熱になります。たとえば、効率が90%の回路で、9[W]=9[J/s]のエネルギーを扱おうとすると、回路への入力は10[W]となり、1[W]が熱になります。このくらいならまだ何とかなりますが、100[W],1000[W]となっていくと、その熱が馬鹿になりません。放熱に失敗すれば、熱容量の小さな部品はあっという間に温度が数百度になって壊れたり、最悪発火します。
エネルギーとしての電気を扱う電子回路は、電力を扱うという意味で、「パワー回路」「パワーエレクトロニクス」と1ジャンルを形成しています。ここでは、メカトロニクス、という立場に立って、機械に動きを与えるアクチュエータの種類と、その電気的な特性をまず紹介し、それを駆動するために必要な回路を示します。
また、狭い意味でのパワー回路である、電源回路についても、ここで併せて紹介します。
なお、一般名詞化した固有名詞が混じっており、往々にして商標ですが、明記はしません。
電気(等)→運動、力の変換を行う部品、装置を総称してアクチュエータといいます(Actuator, Actuate:動かす、作動させる、から)。
俗に「モータ」といっているものも当然アクチュエータで、その大多数を占めます。モータというと、電池をつなぐと回るものとか、100Vをつなぐと回るものといった印象がありますが、かなり原理も様々、品種も様々です。以下、分類した上で、代表的なものを解説します。
分類の観点
以下、いくつかの観点から分類します。
- 動きの形態:
- ◎回転: 電気アクチュエータの主流。モータというとふつうは回転型。往復運動をさせるためには、ボールねじ、クランクなど機構的工夫が必要。
- ○直動: 単純なカチカチ動作は昔から電磁石が使用されてきた。直線的な運動が必要なものに近年採用が進む、いわゆる「リニアモータ」は文字通り、「直動のモータ」である。微細な伸縮を行う圧電系素子も精密分野で使われている。建設機械などでよく目にする油圧シリンダも直動アクチュエータの一種。
- 運動の継続性
- ◎連続: 回転アクチュエータの大半はぐるぐると際限なく回すことができる。例外的には、メータの針のようなものは、回転式でも連続回転はできない。
- ○往復: 直動アクチュエータの大半は往復運動が基本。リニアモータ採用の地下鉄などは直動という範疇で考えていいかは疑問だが(レールを輪にしたら往復でなくなる?)。
※ここでいう往復は運動の限界があるか、という意
- 投入するエネルギーの形態
- ○電圧: 圧電材料によるもの、マイクロマシンのような静電気力によるものなどは電圧駆動型。ふつうのモータもスピーカも「電圧を投入」するが、本質的には「電圧によって流れる電流」が駆動力を発生。
- ◎電流: アクチュエータの大半は電磁石の発展型である電磁アクチュエータであるが、それらはすべて、電流によって動作するアクチュエータである。ふつう、「電圧をかける」と思われることが多く、事実であるが、数式上は電流と考えるのが妥当。なお、電流と力が比例する。
- ※油圧、水圧: このページの趣旨とはずれるが、ロボットに油圧が使われることがある。その場合は、サーボ弁と呼ばれる、電流で精密に制御できる弁を使用して、油圧シリンダなどに油を流す。この場合、ふつうは油圧の装置とみるが、考えようによっては、少しの電流でつくったサーボ弁の動きを油圧によって増幅したと見なすことができる。
また、別の形では、電気モータ+ポンプで油を駆動し、ピストンを直接駆動するタイプもある。この場合は、油圧は減速増力装置(ギアなどと同列)として機能する。油と水の違いは、さびの問題や、漏れたときの悲しさであり、共通して圧縮性がない。
- ※空気圧: 同じく電磁弁で動作させるが、細かな調整というよりはストロークを一気に動くような使い方。圧縮性があるため、それ自体がバネとして作用し、ロボットの動きを柔らかくすることができる反面、ふにゃふにゃになりやすく制御が難しい。油圧水圧には「戻るパイプ」が必要なのに対して、空気はその場で捨てることができるのも利点。
- 供給する電気の形態
- ○直流: 一般に、アクチュエータから出ている2本の線に電気を流すだけなので、扱いやすい。ただし、モータの場合はブラシ、整流子と呼ばれる接点があり、それがノイズを出したり、回転ムラを起こす原因となったり劣化したりする。なお、出力を時間変化させると、信号としては交流となりうるが、「直流でも動く」ものを直流型と分類する。
- ○交流: 一般に、アクチュエータに複数のコイル等を持ち、それに交流電流、交流電圧を与えることで動作する。複数を駆動しなければならない点、正弦波状の駆動電力を作らなければならない点などで面倒であるが、ブラシがないことが大きな利点となり、近年はロボット等で主流になりつつある。
- ○パルス: 広い意味では交流型であるが、明らかに1ジャンルとして分離している。代表はステッピングモータ。複数のコイルに順次電流を通じることで指定確度毎に回転する。前2者がアナログ的な駆動電力を要求するのに対し、オンオフのみで動作させられるため、ディジタル回路、コンピュータとの相性がとても良い。
- その他観点
- つなげば手軽に回るか?: 適当に電源をつないだだけで回るような直流モータはちょっとしたテストもやりやすい一方、交流モータなどは専用の制御装置をつながないと回しがたい。
- 思った通りに動くか?: 電磁アクチュエータの大半は電流で「力」を出力する。そのため、速度や位置を制御するには、センサで検出してフィードバック制御が必要。パルス系も基本はそうであるが、ステップ状に動作する構造のため、動かしやすい。
- なめらかに動くか?: 同じ直流モータでも、マブチモータは制御、という観点からはなめらかさに欠ける。サーボモータと称して販売されているものは極数を多くするなどなるべくなめらかになるように工夫されている。パルス系は大局的にはなめらかでも動くときはごつごつ動き、振動が起きる。
- 対象の向き不向き: 当然ながら、それぞれのアクチュエータには向き不向きがある。おおざっぱには、大型大出力系、小型小出力、微細変位などに分けられるが、電気モータの適用範囲がどんどん広くなりつつある。
- 効率: モータの効率は投入電力に対する出力の力学的エネルギーである。損失は一般に熱になる。直流モータは簡単に回せるが、ブラシの接触抵抗でも損失が起きるため、交流モータに比べて損である。が、交流モータは駆動回路が複雑になる分、回路の作りが悪いとそちらの損失が多くなる。ステッピングモータは明らかに効率が悪い。
代表的なアクチュエータ
| 名称 | 動き・継続 | 投入形態 | 手軽さ | 制御性 | 付記 |
| 直流サーボモータ(DCサーボ) | 連続回転 | 直流電流 | ○ | ◎ | 移動ロボットなどによく使われていたが、近年は縮小気味→交流へ。詳細後述。 |
| 模型用モータ(マブチモータ) | 連続回転 | 直流電流(直流電圧) | ◎ | ○ | なにかを動かすだけなら便利。本来電流駆動であるが、ふつう使うときは電圧で動かすのが一般的。その場合、負荷にもよるが、主に速度が決まる→DCモータの詳細参照。 |
| 交流サーボモータ(ACサーボ) | 連続回転 | 交流電流のセット | △ | ◎ | 近年、ロボット用や生産機械などで主流になりつつある。モータとセットのコントローラが必須でそれをつければ手軽に動かせる。誘導型などモータ本体は種々あり、直流ではないサーボモータともいえる。 |
| ステッピングモータ | 連続回転 | パルス電流のセット | ◎ | ◎ | とにかく手軽に動かせるが、明らかに効率が悪い。駆動方法を工夫してなめらかに回すことが可能で、極めると交流モータと変わらなくなる。詳細は後述。 |
| リニアモータ(同期式、誘導式) | 直動往復 | 交流電流(専用制御装置) | × | ◎ | 磁気浮上式鉄道、地下鉄などで採用される他、大型工作機械で採用される。小型化が進んでいないため、ロボット等にはまだあまり使われず。最大の利点は直接、直線運動することであり、鉄道の場合は車輪の駆動力の制約を除け、工作機械ではネジのバックラッシュや剛性などの問題が無くなり高精度化する。リニアステッピングモータもある。 |
| DCブラシレスモータ(1) | 連続回転 | 交流電流、直流電圧 | ◎ | × | DCモータから接点をなくす、という発想で、電子制御になったモータで交流モータの一種といえる。ブラシが無いため寿命が長く、ノイズが出ないことから電子機器にもよく使用される。小型のものに簡易的な制御を搭載したものもあり、その場合は適当な電圧を加えると適当な速度で回る。制御の対象というよりは、回すだけのモータ。主にパソコンのファンなど。 |
| DCブラシレスモータ(2)(BLDC) | 連続回転 | 交流電流、直流電圧 | ○ | ○ | 最近、主にラジコン分野でポピュラーになりつつあるモータで、実質的には交流モータ。専用のコントローラとセットにして使うと出力可変の直流モータと同じような使い勝手となる。上記と同じ利点は持つが、コントローラが必須になる分だけ手間が増える。 |
| 超音波モータ | 連続回転 | 交流orパルス電流 | △ | ○ | 電圧を加えると変形する圧電材料に電極をつけ、適当な電流を流すことでうねるような動作を起こし、摩擦によって対象を動かす。作りにもよるが、一般に低速な反面、薄型で大トルクを出せる。カメラのレンズのピント調整、ズームなどのメカにも使用される。 |
| ソレノイド | 直動往復(吸引) | 直流電流(On/Off) | ◎ | △ | 電磁石そのもの。一般にはコイルに鉄芯が引き込まれる形態。単純にカチャっと動かしたいところで使う。制御というより単純にオンオフのみで使う。吸い込むだけなので、バネなどで戻す。 |
| ボイスコイル | 直動往復 | 直流電流 | ○ | ○ | ばねで支えられたコイルと永久磁石。電流を流せばコイルが動く。名前の由来はスピーカのコイルと同構造なため。基本的に微少変位。CDやDVDのドライブの、レーザのピントを合わせるためのレンズの駆動に使われている、という観点では身近。 |
| ラジコンサーボ | 回転往復 | パルス指令 | ◎ | ◎ | 本来はラジコン用の部品。手元のコントローラの指示で特定の角度になるような部品。直流モータとギア、角度検出センサ、制御ICがパッケージされたもので、電源と、パルスの指令を与えればよい。その手軽さから近年小型ロボットのアクチュエータとして盛んに使われ、それ専用に開発されつつある。上記サーボモータとの混同に注意。 |
| 形状記憶合金 | 直動収縮 | 直流電力 | ○ | ○ | 電流を流すと加熱して、その熱で結晶構造が変化して収縮力や曲げの力を生じる。加熱は電力の投入で決まるため短時間でできるが、冷却に時間がかかるため、俊敏な往復に難あり。ただし、比較的軽量小型なものも可能である。最近はバイオメタルファイバ(商品名)として入手しやすくなった。 |
| | | | | |
直流(サーボ)モータの特性
ここでは、直流(サーボ)モータの特性を示します。
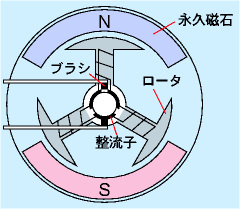 |
| 直流モータ(3極)の構造(トラ技2005-12など参考) |
構造は、右図に示すように、ステータと呼ばれる、固定の磁界を作る部分(ふつうは永久磁石)と、ロータと呼ばれる電磁石からなります。ロータの軸には整流子と呼ばれる接点があり、ここにブラシと呼ばれる外部接点から電流が供給されます。
このブラシと整流子により、ロータの電磁石には、正負の電流が適宜流れ、ステータとうまく吸引、反発を繰り返しながら、回転するように動作します。
図では、一番シンプルな3極のモータ(ふつうのマブチモータはこのタイプ)で書いてあります。この場合、電磁石が並直列に切り替わるため、角度によって電流が大きく変化し、それに伴いモータ自身の発生トルクも、制御回路的にも、特性が角度に依存して大きく変動してしまいます。そのため、俗にサーボモータと呼ばれているモータでは、極数を増やし、コイルの巻き方を工夫し、なるべくなめらかな特性になるように工夫してあります。
直流モータは、小学校の実験で遊んだように、発電機にもなります。これは、モータとして使っていないときだけではなく、モータとして動いているときにも実は起きている現象です。これがモータの特性理解には重要なもので、その発電電圧=起電力は回転速度に比例します。また、電子回路としてみたときには、ブラシ、整流子の接触抵抗、そもそも電磁石のコイルの抵抗があり、また、コイルゆえにインダクタンスもあります。
以上を式に表すと、以下のようになります。
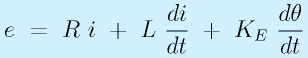
ここで、eはモータにかけた電圧、iはモータに流れる電流です。θは角度、その時間微分値は角速度、KEは(逆)起電力定数と呼ばれる定数でモータに固有です。
また、モータの発生するトルクは、電流に比例します。
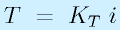 (KTはトルク定数)
(KTはトルク定数)
そのため、モータの特性は、電流にも注目する必要があります。
このモータに電流を流して回すことを考えます。
制御目的で使用する場合、 モータに流す電流 を調整する方法が主流です。この場合、電流を調整できる回路を使う必要があります(アナログ回路の基礎の電流出力アンプの大出力版)。回転速度に応じて起電力が変化するため、回路の出力電圧もそれに応じて変わることになります。
このとき、モータは電流に比例したトルクが得られるため、適当な運動方程式で対象を駆動し、加速度的な動作になります。
つぎに、モータに 電圧をかけて 回すことを考えます。マブチモータを電池につないで回すのも、同じようなものです。
まず、最初停止しているとすると、起電力はゼロです。電源を入れた瞬間、急に電流が増えようとしますが、コイルの影響で徐々に(といっても機械的な時間の流れからすると十分短い)。コイルの影響がないとして、
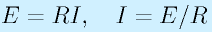
の電流が流れます。この電流でトルクが生じ、加速します。その結果、起電力が増加し、
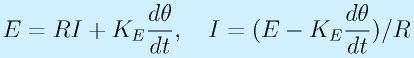
において徐々に電流が減少します。もし、摩擦がなければ、トルクゼロ=電流ゼロまで加速が続き、
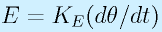
となるところで加速が停止し、一定速度となります。もし、摩擦や駆動力が必要な場合、その分の電流が最低限必要になるため、より低い速度で加速しなくなり、一定の速度となります。
マブチモータに電池をつなぐと「ふぃぃぃぃん」と加速していき、すこしの間があってから回転速度が一定になるのは、このような状態の変化によります。
また、この式より、トルクゼロでよければ、最終的な回転速度は供給電圧に比例(E/K_E)することがわかります。
以上が、直流サーボモータの特性で、制御性を考えると電流を調整できる回路、すくなくとも電圧を調整できる回路が必要なことがわかりました。
モータ回転模式アニメーション
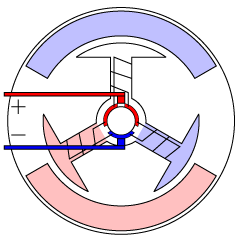
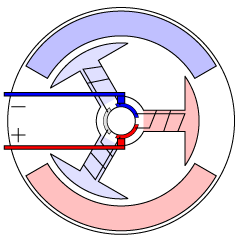
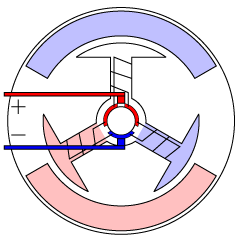
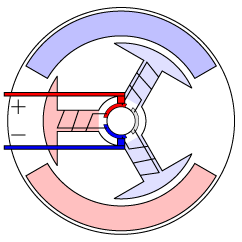
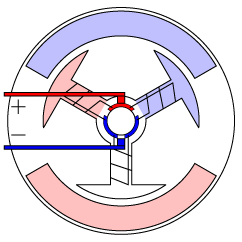
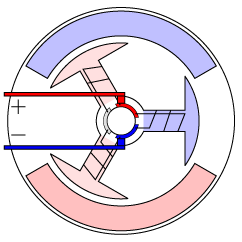
ステッピングモータの特性
ステッピングモータは複数のコイルをもち、それに通じる電流を順次切り替えていくことで、切り替えるたびに一定の角度(ステップ角)だけ回転するモータです。
つまり、直流モータや交流モータのように、単に電流を流せば回るという訳ではありません。
その一方で、切り替え=ステップ角という関係が成り立つため、指定の角度を回したいときは、それに相当する回数だけ切り替えるだけで済みます。直流モータなどは、どれだけ回ったかを別のセンサで検出し、電流を調整しなければならず(フィードバック制御する必要がある)、それに比較すると気楽に使えるモータです。
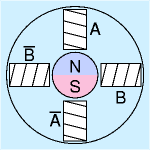 |
| ステッピングモータの概念図(2相型) |
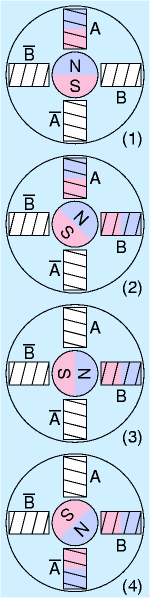 |
| ステッピングモータの回転(1-2相励磁) |
モータの概念図を右に示します。
磁石でできたロータの周りにコイルが配置されています。
このコイルに適当な順番で電流を流すと、磁石がコイルにひきつけられてまわるわけです。
このモータは2相型というタイプのもので、コイルが2系統入っています(ほかに5相型など)。
コイルには、A、B,A−(バー)、B−と名前が付けられています。
右図を例に、モータの回る手順を見てみます。
まず、Aだけに通電して電磁石にします。この場合、磁石はAに引きつけられます。
ここでAを切らずに、Bにも通電します。すると、磁石はAとBの両方に引きつけられ、中間の45度あたりを向きます。つまり、コイルの電流を流し方をかえることで、45度回転したわけです。
つぎにAを切って、Bだけにすると、磁石は横を向きます。ここでも45度回転しました。
最後にA−に通電すると、さらに45度回ります。
この手順を続けることで、4本のコイルを順次8種類切り替えると、360度回ることがわかります。
また、これとは逆順、つまり、A−とB、B、AとB、Bという順で通電すれば、逆方向に回転します。
この駆動方法を、コイルを1本、2本と使うため、「1−2相励磁」と呼びます。コイルを1本ずつ、すなわち図の(1),(3)のみ使う場合、2本ずつ=(2)(4)のみを使う場合を同様に「1相励磁」「2相励磁」と呼びます。
ステッピングモータでいうステップ角は、1or2相励磁の場合のステップ角度をいい、このモータでは90度です。そのため、1−2相励磁を「ハーフステップ駆動」と呼ぶこともあります。
1−2相励磁は、ステップ角が半分になるという特徴が、2相励磁は力が倍近くなるという特徴があります。
このように、ステッピングモータはコイルに流す電流を適切にOnOffすることで、決められた角度ずつ回転します。それと同時に、あるコイルに電流を流しっぱなしにすると、静止状態で固定されます。ステッピングモータは静止時に一番力を出すことができ、速度が上がるとトルクが低下するという特徴をもっています。
さらに速度を上げようとするか、トルクが対象に対して不足するとコイルの切り替えにロータが追いつかなくなる 脱調 という現象が起こり、回らなくなります。多くの場合、ステッピングモータは「コイルを切り替えたので回っているはず」とコンピュータは思いながら操作しているので、脱調は装置として致命的です。
なお、脱調しないまでも、トルクがかかると、本来の位置からはずれます。精密な角度が必要な場合は要注意です。
直流モータがどちらかというと高速回転型なのに対して、ステッピングモータは低速でトルクが大きめなので、直流モータがギア経由で対象を駆動するのに対して、ステッピングモータは直結で動かせるという特徴もあります。
ただ、投じた電流そのものが回転に変わるわけではないため、電流−機械のエネルギー変換効率はかなりわるくなります。
なお、この概念図で示したものはパーマネントマグネットPM型と呼ばれるタイプです。
そのほかに、磁石ではなく、歯車状のロータをまわすバリアブルリラクタンスVR型、両者を組み合わせたハイブリッドHB型があります。
PM型は構造が単純で比較的安価となる一方、ステップ角が粗くなります。
VR型は構造が複雑化しますが、ステップ角が小さくなります。
HB型はステップ角が小さく、かつ磁石の磁力も使うため、トルクも大きくなります。ステッピングモータの多くはHB型です。
(なのに、PMで説明するのは、図をさらっと書くためです。)
以上、ステッピングモータは、コイルに流す電流をオンオフする回路がいくつかあればいい、ということがわかりました。
アクチュエータを駆動する回路は、主にアナログ的に出力するものとディジタル的に出力するものがあります。
前者は、期待する回し方に応じて、ふつうにアナログの電圧を(電流を流すための電圧を)出力します。
比例的、線形的に出力を出す、という意味で「リニア」な回路といわれます。
後者は、短時間で電圧のオンオフを繰り返します。たとえば、時間的に50%くらいの比率でオンオフを繰り返すと、平均的に見れば、半分くらいの電圧がかかっているように見えます。
オンオフを繰り返すことから「スイッチング」型の回路といわれます。
回路構成としては、リニアな回路のほうが比較的単純ですが、一般に効率が良くありません。
スイッチング回路は、そのオンオフのタイミングを決めたり、比率を決めるための回路が必要で、電子回路だけで組み立てると込み入った回路になりますが、効率はリニアに比べて圧倒的に良くなります。
そのため、いまどきのアクチュエータ制御回路の大半がスイッチング型になっています。
ちなみに、スイッチング回路は最近やっと目的の信号の周波数で20kHzくらいが実用になってきました。というのも、20kHzの信号を出すと、その数十倍、1MHz以上のオンオフが必要となり、電力系半導体素子の速度が間に合っていませんでした。それが最近実用になってきたので、オーディオアンプにもスイッチング型が出てき始めています。
以下では、まず、比較的小出力(=効率が悪くても実際の損失が少なめ)であれば十分実用になり、また高速応答が必要な場合に使われる、リニアな駆動回路を紹介します。その上で、スイッチング型を紹介し、その有効性を示します。
※「リニアモータ」の「リニア」と言葉、意味は同じながらも使われ方が違うことに注意。リニアモータを動かすための回路という意味ではなく、リニアモータもスイッチング型で動かされているのが現状です。
電圧駆動と電流駆動
アクチュエータの項で述べたように、電気式のアクチュエータには、電圧駆動型と電流駆動型があります。
それに応じて、駆動回路もねらった電圧を出力するか、ねらった電流を出力する回路をつくってつなぐことになります。
単におさらいしておきます。
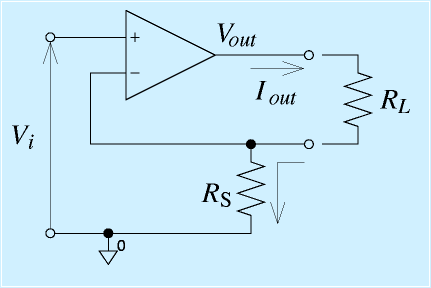 電圧駆動の場合、基本的には、オペアンプによる増幅回路と原理的にはなんら変わりありません。
ただ、ふつうのオペアンプをつかうと、電流が足りないのでモータが回る前にオペアンプの出力が低下するか、熱くなるか、壊れるかします。
電圧駆動の場合、基本的には、オペアンプによる増幅回路と原理的にはなんら変わりありません。
ただ、ふつうのオペアンプをつかうと、電流が足りないのでモータが回る前にオペアンプの出力が低下するか、熱くなるか、壊れるかします。
電流駆動もアナログ回路:増幅回路2の、電流出力アンプ(右図)によって行うことができます。
オペアンプが正しく動くように回路を作った場合、+入力と−入力の電圧は一致するようになります(仮想短絡:バーチャルショート)。それにより、対象である負荷RLを流れた電流によって、電流検出抵抗RSに生じた電圧と、Viが一致するようになる、ということで、ViでRLに流れる電流を調整できるわけです。その場合、その電流が流れるように、オペアンプは適切な電圧を出力します。
つまり、電流出力の場合を含めて、 必要な電流が流せ、必要な電圧を出力できる増幅回路 があれば、電流検出抵抗をつかうか否か、程度の違いになります。
※実際には、対象が単なる抵抗でない場合は、場合によってはオペアンプが正常動作しなくなるため、その改善を行う回路(補償回路)が必要になります。
※このタイプの電流出力回路は、負荷のどちらの端子も電源に(GNDも)接続できません。ただし、このことが実際に問題になることは少なく(アクチュエータはただのコイルだったりするので)、また、アクチュエータ側もある程度それを想定した電気的設計になっている場合があります。
※電流検出抵抗は、対象に流す電流によって選びます。1Aくらいの電流なら1Ωもつければ、1Vになるため、楽に使えます。が、100A流れるときは、0.01Ωで1Vに、そのときは100A×1V=100Wとしゃれにならない損失になります。かといって、電圧が10mVとか小さいとノイズに埋まるなどして逆に危なくなります。抵抗一本ですが、なかなかやっかいです。
電力対応型増幅回路
ここでは、大電力を出せるリニアな増幅回路について見ていきます。
対象に応じて、増幅回路の出力すべき、電圧と電流を別個に見ます。
まず、電圧についてですが、実はやっかいです。次の電流の項で出てきますが、回路を作るときはオペアンプにブースターをつけるような形にします。つまり、オペアンプ自身がその電圧に対応していなければなりません。ただ、ふつうのオペアンプは±15V程度、強いのでも50Vはあまり超えません。そのため、より大きな電圧が必要な場合は、オペアンプの後ろに、より高い電圧まで耐えられるトランジスタによる電圧増幅回路を接続する必要があります。
もっとも、リニアな増幅回路のターゲットで、そういう目にあうことはあまりありません。
次に電流です。世の中の主流である、電磁(電磁石型)アクチュエータは、それなりに電流を流します。
一つめの解決策は「パワーオペアンプ」として開発、販売されているオペアンプを使用することです(LM12, LM675など)。
品種にも寄りますが、数十V,数Aまで耐えられるものは、比較的容易に手に入ります。
それを利用することが一番簡易的で、これまでのオペアンプの使い方はほぼ当てはまります(ただ、特別な回路を追加する必要があることがある)。
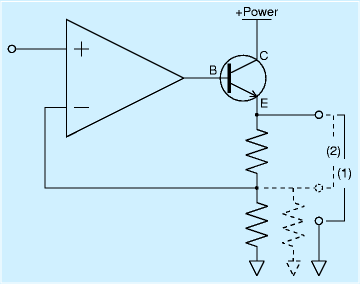 |
| 出力強化オペアンプ回路(1)片電源 |
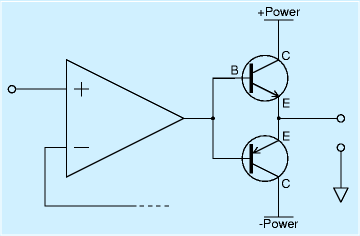 |
| 出力強化オペアンプ回路(2)両電源 |
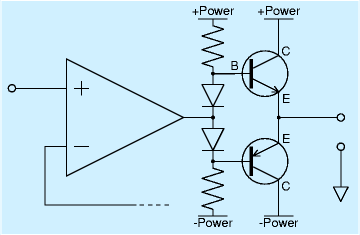 |
| 出力強化オペアンプ回路(3)両電源改 |
もう一つの解決策は、オペアンプにトランジスタを追加して、強化する方法です。
具体的な回路を右に示します。
図(1)は、とりあえず正の電圧だけを与えればいい対象(モータでいえば、1方向回転のみ)に使う回路です。
トランジスタをオペアンプの後ろに直結します(ベース)。コレクタは電源に接続し、エミッタが出力端子になります。
図の実線で示した回路((1)出力)は全体で非反転増幅回路に、破線で示した回路((2)出力)は電流出力回路になります。
この回路において、出力電圧=エミッタ電圧はオペアンプ出力=ベース電圧よりVBE=0.7Vほど低くなります。その意味で、一見すると本来の非反転増幅より0.7V下がってしまいそうにも見えます。が、実際には、オペアンプが0.7V高い電圧を出力して、つじつまを合わせ、それによって+−入力端子間の電圧をゼロとするように働きます。
オペアンプはトランジスタのベース電流を供給するのみで、hFE倍された電流を負荷に流すことができます。
図(2)は、PNPトランジスタを追加して、正負両電源対応にしたものです。この図では、出力周りの回路は省いてありますが、(1)と同等です。ちなみに、(1)の回路もトランジスタをPNPにすれば、負電源側片電源になることに注意してください。
この回路では、正の電圧を出力したい場合、オペアンプはその電圧+0.7Vを出力します。逆に、負の電圧を出力する場合は、オペアンプは-0.7Vを出力します。オペアンプからするとゼロ近辺で1.4Vのギャップが生じますが、モータを回すような用途ではおおむね問題ありません。
この1.4Vのギャップを往復するとき、少なからず影響はあります。オペアンプを使っているのでほぼ帳消しにはしてくれますが、トランジスタの部分としてはこのように0V近辺で出力が出なくなることから、アナログ増幅の世界でクロスオーバ歪みと呼ばれています(C級増幅)。
それをある程度解消するのが図(3)です。VBEで0.7V目減りする分を、ダイオードのVF=0.7Vで最初からかさ上げしておきます。つまり、オペアンプ出力よりVF=0.7Vだけ高い/低い電圧をトランジスタのベースに供給し、VBEで0.7V低下/上昇する分を相殺します。
ただし、この場合、ベース電流は図で追加した抵抗から供給しますし、普段からある程度電流を流しておかなければならないので、無駄が生じます。音質重視のオーディオアンプをつくるのでもなく、モータを回す、電磁石で力を出す、程度なら、(2)で十分です。
ちなみに、こういう対称な回路を作るとき、トランジスタは特性の似たものを使うことになります。これらは「コンプリメンタリ」なトランジスタと呼ばれ、メーカから各種販売されています。
なお、(1),(2)の回路ではオペアンプの出力電圧範囲より0.7V内側の電圧しか出力できず、(3)でもオペアンプの出力範囲しか出ません。ので、この回路はオペアンプの電圧に制限されます。より大きな電圧を出力するには、オペアンプの強いのを使うか、間に増幅回路をトランジスタで作るかになります。が、その前に次節のスイッチング回路を作ってしまった方が早いでしょう。
と、回路はくめますが、じつはやっかいなのは、そこの電源を供給する電源回路です。
増幅回路は打ち出の小槌ではないので、エネルギーそのものは増幅回路の外から供給されます。
ピークで30V10Aをアクチュエータに流したい場合、余裕をみて、たとえば、35V15Aくらいの電源、しかも正負を供給する必要があります。
実は、パワーオペアンプをつかって増幅回路を簡単にすませても、ここのところが難儀だったりすることもある、ということを記憶にとどめておくといいでしょう。
つぎに、リニアと対極を成す、また現在主流となりつつあるスイッチング型の回路について示します。
スイッチング回路
スイッチング回路といっても、特殊な部品を使うわけではなく、リニア回路とおなじトランジスタを使います。
ただ違うのは、リニア回路の場合は、ある意味「限界の範囲内」で使うのに対して、スイッチング回路では「限界over」で使います。
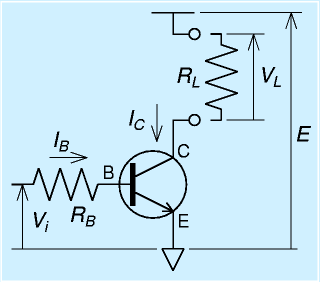 |
| スイッチング回路原理図 |
右の図で具体的に説明します。この図において、以下の式が成り立ちます。
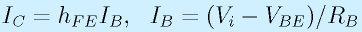
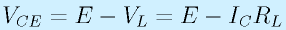
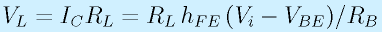
ここで、抵抗RLは、ここで駆動対象として考える負荷です。
Viが十分小さい場合、IBは小さく、hFE倍してもICがそれほど大きくならず、Viの変化に対して、VLは直線的に変化します(VBE分がなければ比例)。
それに対して、Viがある程度大きくなると、この式だけではVLが大きくなるに従ってVCEが負になります。実際には、VCEが負になることはなく、それ以上はVLは大きくなりません(いくらがんばってもVLはEを超えることはない)。そのときの最小のVCEはVCE(sat)といい、トランジスタに固有ですが、ここでは簡単のため、ゼロまでいったとしましょう。
Viの増大に伴って、IBが増加し、VLが限界までいったとき、すなわち、VL=EとなるときのIBは、
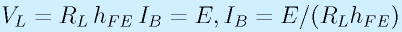
です。これ以上はIBを増やしても、VLは増えません。
この、VLがこれ以上増えない状況と、IB=0でVL=0となる状況のみを使うのが、「スイッチング」です。
前者をオン、後者をオフと見なします。
実際には、hFEのばらつきなどを加味し、しっかりオンとするために十分大きなIBが流れるように、Viのオン、オフを決める電圧からRBを決めます。
そのViは、往々にしてディジタル回路からの信号です。
なぜ、こんな極端な状況だけを使う意味があるかは次で比較します。
リニアとスイッチング
リニアとスイッチングの比較を行います。
まず、第一に、リニアは連続的に出力が可変できるのに対して、スイッチングはオンオフのみで中間がありません。ただし、後述のPWMとよばれる手法でスイッチング型でも中間がつくれます。
(そもそも、ステッピングモータなどオンオフだけですませるものも多いので、その場合はまったく気にする必要なし)
次に、効率です。
先ほどの回路で、トランジスタで消費される電力を考えてみます。
どんな部品でも、流れる電流と端子間電圧の積が電力で、ふつうは熱になります。
トランジスタの場合、ベースに関しては微々たるものなのでふつうは無視して、コレクタ電流に着目します。
まず、リニアな動作の時、
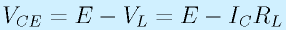
の電圧がCE間にかかり、かつ、電流I_Cが流れます。よって、
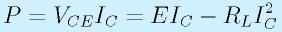
の電力が、トランジスタで熱になります。つまり、ターゲットにある電流を流そうとすると、それに応じて(ここでは2次関数)熱がでます。これが回路としての効率を低下させます。具体的には、
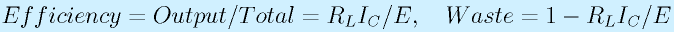
です。ちなみに、先ほどの式から、RLIC=VL=E/2となるとき=ちょうど電源の半分の出力を出すときが、無駄が最大になる、最悪の状況です(ちなみに、効[率]はVLが小さいほど悪い)。
それに対して、スイッチングな時は、2種類の状況です。
- 電流最大(E/RL)、VCEが最小(≒0)→電力小
- 電流ゼロ、VCE最大(VL=0)→電力0
となり、結局、オンオフの状況ともにトランジスタでの消費電力はほぼありません。熱になってしまう無駄分がほぼゼロ、すなわち、効率が高いことになります。
熱は出てしまったら放熱しなければなりません。効率だけではなく、その意味でも、スイッチングのほうが優れているといえます。(立派なオーディオアンプが重いのは、大電力でリニアな動作をさせるために、副作用として出る膨大な熱を放熱するための放熱板のせいです)。
最近は、このスイッチングにMOS-FETを使うことが多くなってきました。図の、バイポーラトランジスタを単にスイッチング用のMOS-FET(パワーMOS FET)に置き換えれば動作します。その場合は、MOS-FETの性能表にある、「オン抵抗」という項目に着目します。MOS-FETはオフの時は高抵抗、オンの時は低抵抗として振る舞うと考えるとわかりやすく、その抵抗値がオン抵抗です。おおむね1Ω未満で、ミリΩ単位でかかれることも良くあります。この場合の電力損失は、IIRで求まります。
なお、この例では、負荷が抵抗なので、電圧のオンオフ=電流のオンオフになっていますが、スイッチングするものは電圧であると考え、電流はそれに応じて変化する、と考えてください。
PWM駆動
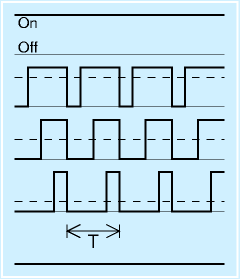 |
| PWM原理図 |
さて、スイッチングのほうが効率などの面でいいことはわかりましたが、「中くらいの出力」を出せないと、出力調整には使えません。それを行うのがPWM方式です。
PWMはパルス幅変調(Pulse Width Modulation)の略です。
変調、とは、ある信号を別の信号に乗せるための信号の加工のことをいいます。たとえば、ラジオで知られる AM,FMはAmplitude/Frequency Modulationの略で、振幅/周波数変調です。これらは、音声信号の波形の電圧値の大小を、正弦波の振幅と周波数の高低に置き換えます。ラジオの側ではそれをまた変換して音声信号に戻すわけです。
それに対して、PWMは文字通り、ある周波数を持ったパルスの幅を変化させます。
右図にその概念を示します。図に示すように、基本的に周期Tでオンオフの矩形波(方形波)です。
ただし、「オンの時間」と「オフの時間」の比が異なります。上から100%(常にオン), 75%, 50%, 25%, 0%(常にオフ)です。
これを対象の変化に比べ、十分に速い速度でオンオフを繰り返します。
その場合、対象から見ると、オンオフの波形そのものではなく、破線で示した、平均的な値が入力されているような状況になります。
つまり、パルスの幅を連続的に変化させれば、そのときどきの平均値も上下するわけです。
この時の周期Tの逆数(f=1/T)をPWM周波数と呼びます。また、オンの時間「比率」を デューティ比 といいます。
これは、平均的には「中間の値」がありますが、あくまでオンオフのみなので、スイッチング回路の利点は生きています。
「平均的に見て」と考えれば、それなりに納得はいくと思います。
このPWM方式の難点は、パルス幅と平均出力が単純には比例しないことです。そのため、あらかじめその関係を確認しておくか、フィードバック制御によって随時調整する必要があります。
また、電磁アクチュエータは少なからずスピーカと同じような性質を持ちます。その結果、このPWM周波数の音が可聴域にあると、音として聞こえてきます。一般に「ひー」「ぴー」という耳障りな音なので聞こえないように20kHz以上に設定することが多いのですが、実験用のロボットなどでは「動作確認音」代わりに10kHz程度にすることもあります。
同じパルス系の出力方法には、オン時間を一定のまま、周波数を変える方法(PFM)や、別の仕掛けでオンの大きさも変えてしまうような方法(PAM)、などもあります。
現実的なスイッチング回路
この信号を実際の対象に出力するための回路を考えます。
まず、単純な抵抗であって、インダクタンス=コイル分が全く無い場合、先ほどのスイッチング回路はそのまま使えます。
問題は、インダクタンスがある場合です。電磁石系のアクチュエータはまさにコイルなので、ほぼ確実にこちらの場合になりますし、アクチュエータではありませんが、リレーと呼ばれる、一種の電磁石によるスイッチ部品も該当します。
コイルの性質は「電流を流そうとしても増えにくく、切ろうとしても減りにくい」です。
この増えにくい性質は、さしあたって致命的な害は成しません。ただ、立ち上がりが悪いとトータルでは期待通り出力が出なくなります。
問題は減りにくい性質です。ある程度電流が流れているコイルをスイッチなどで切り離します。すると、電流がゼロに一瞬で変化せざるを得ません。その結果、コイルの電圧
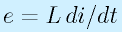
は、di/dtが負の大きな値となるため(変化大)、極端に大きくなります。場合によっては火花が散ります。この電圧を、最初かけていた電圧と逆の電圧が発生したように見えることから逆起電力と呼びます。
自動車のスパークプラグで火花を飛ばすのはこの原理の応用ですし、スイッチをオンオフしたときに隙間から火花が見えるのもこれが原因です(たとえその先が電球であっても、そこに至る長い電線がコイルの性質を帯びる)。
で、この大きな電圧は、トランジスタに極めて有害で、わりとあっさりと破壊に至ります。
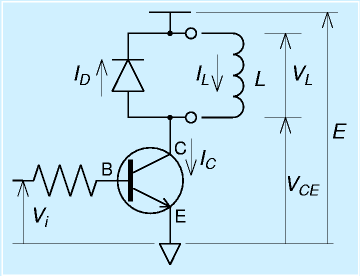 |
| コイル対象のスイッチングの場合 |
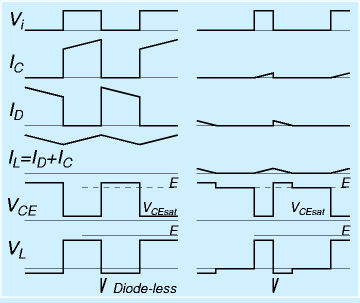 |
| PWM駆動時の各部の電圧、電流 |
これを防ぐため、ダイオードを使います。
具体的には、先ほどの回路に、右図のようにダイオードをつけます。ダイオードの向きが逆なようにも見えますが、上向きで正常です
(下向きにつけると、オンの時に流れてしまうので、そもそもNG)。また、純粋なコイルということはなく、ふつうは抵抗分を考えますが、ここではコイルのみを考えます。
ダイオードが無い状態で、トランジスタをオフにすると逆起電力が発生します。電流変化がマイナスなので、電圧もマイナスにでます。コイルに出る電圧がマイナス、ということがどういうことかというと、これまで電圧は一方を基準にしてきました。右図では、コイルの下端を基準に、電圧VLをとっています。上端の電位が高いときが正です。
負ということは電位でみて、上端が低い状態、逆に上端を基準にすれば下端の電圧が高い、ということです。
逆起電力ではこれが極端にでますが、それはそのままトランジスタのコレクタにつながっています。コイルの大きさ、トランジスタの耐性にもよりますが、状況によっては一撃で破壊します。
ここにダイオードをつけると、コイルの上端に比べて、コイルの下端の電圧が高くなったとき、ダイオードに電流がながれ、その両端は順方向電圧降下VF(0.7V、ただ大電流の時は1Vを超えることもある)よりは電圧が高くなりません。
ダイオードの上端=コイルの上端は電源電圧Eで固定されているため、各下端=コレクタはそれよりもVFだけ高い電圧に制限され、壊れる心配が無くなります。
このダイオードのことをフリーホイールダイオードよびます。
(諸説ありますが、とりあえず「フライ」ホイールという呼び方は割と広く出回っている、日本限定方言です。free-wheelです。語源は自転車の、ラチェットが入っている、車輪を一方向のみに駆動する部品の名前のようです。日本語で転流ダイオードと呼ばれることもあります。)
右図に、各部の電圧、電流の概念図を示しました。
それぞれの状態(トランジスタがオンかオフか)と、コイルの性質などをもとにすると、だいたいこんな感じに動くことが推定されます。
実際の回路でも似たような信号が観測されます。
PWMのデューティ比が十分高い場合、対象に流れる電流ILは波打ちますが、その電流はトランジスタとダイオードを交互に流れています。電圧オンで電流が増加し、オフ時にはダイオードなどもろもろの損失で電流が減っていきます。それが適当に釣り合うところで、電流が決まりますデューティ比が小さい場合は、十分に電流が上がらなく、オフ期間の途中で力尽きます。
ちなみに、VCEでEより上に飛び出ているのは、VFの分です。また、ダイオードがなかったり、速度が遅いとVLの下に書いた逆起電力が発生し、(図で明記していないものの)VCEで正の方向にでることになります。
ここで使っているダイオードは、何でもいいわけではありません。トランジスタがオフの間、コイルに流れる電流を引き受けるため、それ相応の電流に耐えられること(基本的にもとの電流を超えることはなし)、また、ダイオードがオフ→オンとなるのにも時間がかかりますが、これが十分に速いこと(さもなければ先に電圧が上がってしまってトランジスタが壊れる)などが条件です。適当につくるときは、適当なダイオードを使いますが、本気で大電力をつかうときは、ファーストリカバリダイオード(FRD)とよばれるものをつかいます。また、効率を重視すると、このダイオードで生じる損失(VF×IDは損失になる)を減らす工夫などをします。
さらに、PWMにつかうときには、このダイオードとそこを通る電流は重要です。図のようにトランジスタで電流をPWMでオンオフしている(この電流が電源からの電流でもある)にもかかわらず、「コイル電流」はそれほど変化せず、平均的に流れるのに役立つからです。一方で、単なるオンオフをスイッチする目的の時(ステッピングモータなど)の場合は、トランジスタをオフにしてもコイルに電流が流れ続ける=磁力がオフにならないと、逆効果です。その場合、ダイオードに直列に抵抗をいれ、抵抗で熱に変えてしまうことで電流=コイルのエネルギーを減少させます(その抵抗の電圧降下分だけ、コレクタ電圧が上がるので注意)。
特にステッピングモータのコイルのスイッチングを行う場合、
- コイルは電圧をオンにしても電流がすぐには流れない→電流が全体で目減り→磁力が減る
- オフにしたときは、ダイオード経由の電流がすぐにオフにならない→次のコイルに磁石が回りにくい
という二つの理由で、回転数が高い=速いスイッチングが必要な場合、トルクが落ちてきます。
そのため、いかにコイルに無理矢理流すかでいくつか方法があります。→メカトロニクス入門 P126に詳しい説明
PWM信号の作り方
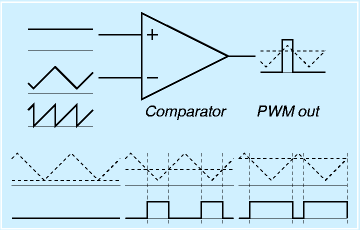 |
| PWMの生成方法 |
PWM信号を作る方法にはいくつかあります。
「PWM信号を作る」=「ある入力値(設定値)に対応したパルス幅を作る」で、PWMを作る場合の入力は何らかの出力設定値、出力はPWM信号です。
基本的な原理を、右図に示します。
PWMを作るためには、三角波(鋸歯状波含む)とコンパレータを用います。
原理は単純で、三角波と出力設定値をコンパレータで比較します。
コンパレータは、+端子が−端子よりも高い値ならオンを、+端子が低ければオフを出力します。
つまり、三角波のある時刻での値の大小と、出力設定値を比較し、設定値が三角波よりも高い値の間だけオンになります。
これにより、「設定値が高いほど、オンの時間が増える」というPWMの性質にそう信号を作ることができます。
この方法は、アナログ回路、ディジタル回路、ソフトウエアで作ることができます。
アナログ回路で作る場合は、三角波発振回路(コンデンサの充放電で電圧の変化をつくる)と、コンパレータを使います。
コンパレータはオペアンプと似た部品で、+−端子の電位差を極端に増幅=大小が出力にはっきり出す部品です。
ただし、オペアンプは増幅回路として動作するよう工夫されているのに対して、コンパレータは比較に特化し、その分高速な動作が可能です。あとは、設定値はアナログ電圧でいれます。
ディジタル回路で作る場合は、カウンタとディジタルのコンパレータを使います。
たとえば、4ビットのカウンタに、一定周波数のクロックをいれると、クロックが入るたびに0→1→...15→0(桁あふれ)→1..と数えます。これが鋸歯状波になります。
ディジタルのコンパレータは、2系統の入力をそれぞれ2進数と見なして大小を判断する回路です(8bitくらいまでは簡単に入手できます)。
設定値は2進数ディジタル値で与えることで、そのままディジタルなオンオフが作れます。
ソフトウエアで作る場合は、一定の周期で値を増やす変数(これもふつうはカウンタという)と、設定値をif文で比較して、オンオフを決めるだけです。
アナログの場合は、三角波が作りやすいので三角波、ディジタルは鋸歯状波が作りやすいので鋸歯状波、という違いはありますが、基本的には同原理です。
いまどきは、PWM信号はモータを制御するマイコン等に内蔵する専用回路で作ることも多く、その場合は、2つめのディジタル回路と同等な原理の回路が入っています。
Hブリッジ
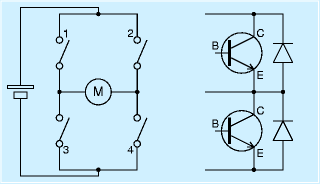 |
| Hブリッジの構成 |
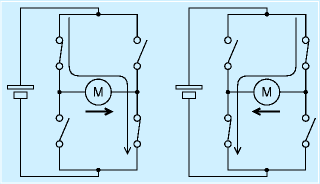 |
| Hブリッジの原理 |
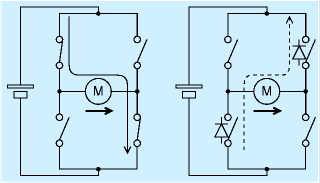 |
| Hブリッジにおける転流 |
さて、ここまでのスイッチング回路は「オンオフ」しかできません。
しかし、ロボットのモータを動かしたい場合などは、当然、「正転・逆転」もさせる必要があります。
この目的で使用される回路がHブリッジ回路です。
右図にHブリッジの構成を示します。駆動したい対象(ここではMで示したモータ)の周りに、スイッチ4個で回路を作ります。
スイッチといっても、トランジスタ、MOS-FETによる電子スイッチです(手動で操作するくらいなら、物理的なスイッチでかまいませんが)。この回路の形が「H」字型なので、Hブリッジと呼ばれています。
この回路の動作を見てみます。スイッチは、対角の位置にあるスイッチ=1&4、2&3を対にして考えます。
まず、1&4のスイッチをオンにします。このとき、電源より、1→M→4という経路で電流が流れます。結果的に、対象には図で右向きの電流が流れます。
逆に、2&3のスイッチをオンにします。このとき、電源より、2→M→3という経路で電流が流れます。結果的に、対象にはずで左向きの電流が流れます。
このように、対となるスイッチのいずれかをオンすることで、電流の方向も変えられます。
PWMするときは、このスイッチをPWM信号にあわせてオンオフします。
なお、間違っても、1&3,2&4が同時にオンするようなことはあってはなりません。厳密に言えば、トランジスタなどによる電子スイッチはオンオフにはわずかながら時間がかかります(しかも、一般にオフになるのが遅い)。1&4,2&3を頻繁に切り替えるような場合は注意が必要です。
さて、スイッチングするときは、先の逆起電力および転流を考えなければなりません。
そこで、実際の部品で回路を作る場合は上の図のように、トランジスタ等に並列に、上向きにダイオードを入れます。
一番下の図で、このダイオードの働きを見ます。
1&4のスイッチをオンして、対象に右向きの電流が流れたとします。これをオフにした直後は、やはり右向きの電流が流れ続けようとします。この電流がどうやって流れるかというと、3のダイオード→M→2のダイオードと流れます。
ただ、ここで注意しなければならないのは、この電流、電源に帰って行く方向に流れます。電源より逆起電力のほうが大きければ、電流は電圧の高い方→低い方に流れる、という観点で、当然のように電源に帰って行きます。
多くの電源は、逆流は許さないものが多いため、注意が必要です。が、モータに使うような電源は、たとえば、充電池がそのままつながっていたり、大容量のコンデンサがついていたり、吸収できることも多く、問題にはなりません。
この電源に帰る電流を避けるためのもう一つの方法として、4のスイッチをオンにしたままで、1だけPWMでオンオフするという手もあります。この場合、3のダイオード→M→4というループで電流が流れます。
このHブリッジのもう一つの面白い特性は「回生」です。
モータは発電機ともなります。たとえば、電車はブレーキをかけるとき、まずはモータを発電機にして、運動エネルギーを電気エネルギーの形で吸い取り、それを架線に返します(この電気はどこか遠くの別の電車が使う)。電気自動車も同様に発電して、バッテリーに蓄えます。この発電動作を「回生ブレーキ」といいます。
まず、単純に、モータがガンガンまわっているとき、そのまま発電した電気=発生した電流がダイオードを通って適当に電源に帰ります。
が、実際にはそれほど単純ではなく、モータの原理では、発電機分=起電力=電源電圧のところで回転数が上限となります。つまり、下り坂などでそれを超えるスピードでモータが回らない限り、単純には充電できません。
そこで実際には、ブレーキをかけたい方向に、一度スイッチを短時間オンして、モータのコイルに電流を流すきっかけをつくってやります。それがそのまま流れ続けて帰ってくる、といった感じで動きます。
詳細はかなり複雑なので避けますが、指定した電流を流すように、PWM幅をうまく制御すると、必要に応じてモータとして動作したり、発電機として電気を戻したりが自動的に起きる、くらいおぼろげに覚えておけばいいと思います。
(消去法的な考え方としては、回生ブレーキをかけて、熱にもなっていなければ、運動エネルギーは電気にもどるしかない、という考え方もありです)。
以上、いまどきのモータ制御回路は、このHブリッジ方式で、PWMをかける、という形態がふつうです。俗に「インバータ」と呼ばれる、交流モータの駆動回路も、この系統です。
実際に、Hブリッジをばらの部品で作ろうとすると大変です。図の下側のトランジスタ(FET)(=ローサイドスイッチという)をオンさせる(=VBEに0.7V以上かける or VGSに適当な電圧)のは比較的簡単です。それに対して、上側(=ハイサイド)をオンにするには、オン状態=エミッタ側がモータの電源(一般に数十Vなど)に近くなった状態でVBEをかけないといけないため、ベース電圧は電源を超えます。そのための工夫が必要になります(専用ICを使うと楽)。
大電力に対応するには、バラの部品で作る必要がありますが、30V、3Aくらいであれば、「HブリッジIC」「Hブリッジドライバ」なる、電源とPWM信号だけをつなぐと動くような小型のICがあり、それを使うと非常に楽に動きます。
電源回路とは
「回路に電気を供給する回路」=「電源回路」もパワー回路の一種です(文字通り、「パワー」の回路)。
一般に、電源回路というと様々な種類がありますが、ここでは、オペアンプの回路やディジタル回路に電源を供給する回路について簡単に見てみましょう。
これらの回路に求められることは「一定の電圧で」「十分な電流を」供給することです。
いままで扱ってきた回路のうち「電圧供給型」のパワー回路は、指定した電圧を、対象に流すような回路です。
いままでは対象がモータなどのアクチュエータでしたが、これが単に「電子回路」だと考えるだけです。
また、アクチュエータの駆動回路は、多くの場合、時々刻々と供給すべき電圧が変わりますが、電源回路の場合は一定の電圧を供給するのみです。
これまでの駆動回路同様、電源にもリニアなタイプ、スイッチングなタイプがあります。
トランス、整流回路、平滑回路
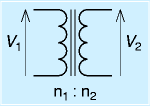 |
| トランス |
これまでのパワー回路にも電源が供給されていたように「電源回路」にも電源が必要です。ただ、一点異なるのは、電源回路に取っ手の電源は、一般に「質の悪い」電源で、それをきれいにして、後ろの回路に与える、という形態です。
ここでいう「質の悪い」とは、電圧が一定しない(短期的には電圧が波打った電源、長期的には徐々に電圧が下がる電池なども)ことを意味します。
電池や充電池を使わない多くの場合は、電源はコンセントの交流からとります。これを使いやすくするため、三つの作業が必要です。
一つ目は、コンセントは交流100Vであり、15Vや5Vで動く回路にとっては、電圧が高すぎます。これを下げることが必要です。
それによく使われるのがトランスです。
ただし、トランスは一般に鉄のかたまりで重いため、いまは大きなトランスを使うことが少ない、後述のスイッチング電源が主流です。
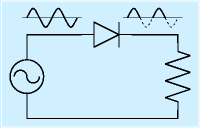 |
| 半波整流回路 |
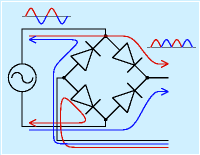 |
| 全波整流回路(ダイオードブリッジ) |
二つめは、正負の電圧で変化する交流を直流までいかなくとも、正の電圧だけに直すことで、これを「整流」といいます。
具体的には右図のような回路をつかいます。
単純にはダイオード1本つかえば、一方向にしか電流が流れず、結果的に正の電圧だけを伝えることになります。
ただし、この場合、間にゼロになる区間があり、次に行う平滑の荷が重くなります。
そこで、広く使われているのが、ダイオード4本を組み合わせた「ダイオードブリッジ」と呼ばれる回路による整流です。
正の電圧が来た場合、負の電圧が来た場合でダイオードが2本ずつ交互に導通し、どちらの場合も正の電圧として出てくるように工夫されています。部品点数が増え、ダイオードの電圧降下も2倍にはなりますが、効率面からこれが一般的に使われます。そのため、最初からダイオード4本を一つのパッケージにしたものもいろいろ市販されています。
なお、一般に、○○Vの交流といった場合、ピークは√2倍の電圧を持ちます。そのため、負荷にもよりますが、整流後の電圧は高めになることがあります。
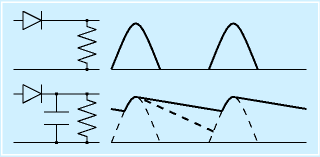 |
| コンデンサによる平滑 |
最後が平滑です。整流しただけでは、電圧がゼロに落ちるところがあり、とてもですが回路では使えません。そこで、コンデンサを追加し、コンデンサに電気をためることで、その期間を乗り切ります。
右図にその概念を示します。
コンデンサを追加することによって、コンデンサより入力の電圧(交流側)が高いときはダイオード経由でコンデンサが充電され、入力側が落ち込んだときはコンデンサからの放電で後続の回路=負荷に電流が供給されます。
一般に充電はほぼ追従してなされますが(その分、充電期間には、平均電流を上回るパルス的な電流が流れる→ノイズの原因になる)、放電は、負荷にどの程度の電流が流れるかとコンデンサの容量で決まります。もし、コンデンサが負荷に比べて小さい場合、破線のようにより速くコンデンサの電圧が低下します。後述の安定化回路に入力すべき電圧、入力される交流のピーク電圧、必要な電流量などを考慮の上、コンデンサは大きめにします(これまでの回路のコンデンサが1μFもないのがふつうだったのに対して、電源で使うコンデンサは数百〜数千μFがふつうです)。
ここでは半波整流回路を例にしましたが、全波の場合は当然「充電できない期間」が大幅に短くなり、同じ負荷、同じコンデンサでも電圧の落ち込みが小さくなります。それが全波のいいところですが、負荷に電流がほとんど流れないようなら、半波でも十分なことがあります。
ここまでで、不完全ながらも交流が直流っぽく変わります。
これで動く回路もありますが、一般には、この後電圧の安定化を行います。
シリーズレギュレータ(三端子レギュレータ)
上の電力対応型増幅回路をつくり、その入力を一定の電圧(基準電圧)にすれば、一定の電圧で、それなりの電流を出力できるようになります。これは、負荷としての回路に、一定の電圧を供給できる回路、と言えます。
たとえば、基準電圧を1V,分圧抵抗比を4:1にすれば、5Vを出力する回路ができます。また抵抗を可変抵抗にすれば、電圧を変えることもできます。
回路全体を一つの固まりとしてみると、整流・平滑回路などの直前の電源回路(すでに安定化された電源なども含む)から、この回路を通って、一定の電圧が出てくる、という形になります。電源の配線に直列に挟むような形であるため「シリーズレギュレータ」(シリーズ=series、直列/レギュレータ=regulator、調整器)と呼ばれます。
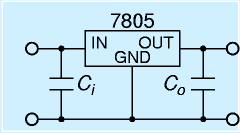 |
| 三端子レギュレータ回路 |
繰り返しになりますが、一つの固まりとみると、電源の入力、安定化された出力、それと基準となるGNDだけが外部とつながる線と言えます。そこで、この回路をワンパッケージにした電源用のICが広く使われています。足が3本ということで「三端子レギュレータ」と呼ばれています。部品屋さんで「三端子」というだけで通じるくらいポピュラーな存在です(トランジスタも、FETも足は3本ですが、三端子といったら、電源用のこの部品)。
具体的な使い方は右図のように、目的の回路(右側)と、元々の電源側(左側)の間に、三端子レギュレータ本体と、コンデンサをセットで挟みます。
コンデンサCi,Coは三端子レギュレータの動作を助けるもので、各メーカの製品ごとに、推奨値が異なります。一般に、0.1μ〜10μ程度です。このように非常に簡単に目的の電圧が得られ、しかも値段も100円もしない、便利なものです。
上に7805と書いてあるのは、5V用の三端子レギュレータの一般的な型番です(これにメーカ毎にいろいろアルファベットなどの記号がつく)。もちろん他にも品種がありますが、三端子レギュレータ=78??というくらい、これもまた一般化しています。ちなみに、負の電圧を作る(負の電圧→絶対値を下げた負の電圧で正負が変わるわけではない)ためのものは79??です。
このシリーズレギュレータは、後述のスイッチングレギュレータに比べて、これまでの話同様に効率が悪い反面、スイッチングに伴うノイズが出ない=クリーンな電気を作りやすいという特徴があります。そのため、アナログ回路の電源ではよく使われます(スイッチングレギュレータである程度大きめの電圧を作った上で、シリーズレギュレータで目的ぴったりに落とす)。ただ、その効率の悪さ故、放熱には気を遣う必要があります。たとえば、12Vくらいを5Vに落とすとき、1A取ろうと思ったら、(12−5)×1=7Wの熱が生じます。これもまた、電力は小さめな用途向け、と言えます。
スイッチングレギュレータ・DC-DCコンバータ
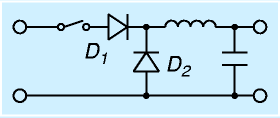 |
| フォワード型SWレギュレータ |
リニア型の回路に対して、スイッチング型の回路もあります。
スイッチング型の電源回路は目的に応じていくつかありますが、ここでは代表的なものを紹介します。
右図は、フォワード型と呼ばれるスイッチングレギュレータの原理図です。
スイッチをオンするとダイオードD1を通じて、コイルに電流がながれ、コンデンサに充電しつつ、後続の回路に電流を供給します。スイッチをオフすると、コイルの「電流を流し続ける特性」により、コンデンサへの充電電流+供給電流はいきなりゼロにはならず、ダイオードD2を通じて流れ続けます。もちろん、徐々に低下するので、コンデンサからの持ち出しも始まります。
スイッチは、PWMによってオンオフします。そのPWM幅は出力電圧を監視しながら、調整します。出力が下がってくるようなら、デューティ比をあげ、出力が過剰になったらデューティ比を下げます。
(つまり、この図の回路の他に、多少ややこしい制御回路が必要)
もとの電源からの電流はスイッチのオンオフで断続的ですが、それをコイルとコンデンサに貯めたり出したりしながら、後続の回路には安定した電圧、電流を供給するという回路です。
ただし、このオンオフによる瞬間的な電圧などの変化は完全に消すことはできず、ノイズや電圧変動として残ってしまいます。
ディジタル回路くらいなら全く問題ありませんが、アナログ回路に使う場合には問題になることがあります。
この回路は、直流の電源を、別の電圧の直流の電源に直す回路で、「DC−DCコンバータ」と呼ばれます。
この回路は、電圧を下げることしかできず降圧型コンバータ、また、GNDが共通であるため、非絶縁型と分類されます。
このほかに、「コイルに電流を貯める」ことでより高い電圧に上げることが可能な昇圧型、どちらも可能な昇降圧型などもあります。また、間にトランスをいれることで、絶縁したものもあります(ややこしいことに、トランスを使っても絶縁じゃないタイプもあり)。
一般的なスイッチング電源という場合は、AC100Vをいれて、5Vや15Vなどを得るための電源回路です。
構造的には、一度100Vを整流・平滑して100V以上の直流にし、これを低電圧の直流に変換します。100→5などにすると、デューティが極端に小さくなるため、間にトランスをいれて落とします(スイッチングした電流は交流としての性格を強く持つため、トランスで変圧可能)。また、これにより、絶縁も行います。
※AC100Vはさわると1/2の確率で感電します。整流しても感電は防げませんので、それを普段さわる回路と共通のGNDを持たせたりすることはできません。
なお、前述の「AC100Vを直接あつかうトランス」は一般に大型重量物ですが、スイッチング電源のトランスは比較的小型です。これは、AC100Vは50Hzと周波数が低いのに対して、スイッチング電源は数十kHz以上と周波数が高いことによります。
以前は電源回路というと「重いトランス」というイメージだったのですが(昔のACアダプタがずしりと重いのはトランスのせい)、最近は部品点数が多くともスイッチング型が主流で、回路も小型軽量化が進んでいます(最近のACアダプタで軽いのはスイッチング型。大きさの割に電流も大きい)。
以上、スイッチング方式の原理を述べましたが、実際に自前で電源回路を設計しなければならないことは希で、ふつうはモジュールとしての電源を買ってくることがふつうです。ただ、性質として「スイッチングゆえのノイズがある」ことは頭に入れておいたほうがよいでしょう。
三端子レギュレータによる電源は、簡単に作れますので、覚えておいて損はありません。
電源に関する一般論
電源を供給する線、電気が流れればどんな線でもいいというわけではありません。
モータなどに電流を供給する線もそうですが、線は細いほど抵抗が高くなります。そのため、大電流を流す線ほど太くする必要があります。
それと同時に、電線を一本引いたら、それは僅かですがコイルとしての性格を持ちます(くるっと巻いたりしたらはっきりと性格がでます)
。電源がつながる回路は、回路の動作によって流れる電流が変わります(特にディジタル回路)。
電流が変われば、コイルでは電圧が発生します。その結果、回路に供給される電圧が電流変化に応じて変動することがあります。
これを避けるため、電源とGNDの線にはあちこちコンデンサを挟むことが実際の回路を動作させるときの基本です。電流が急に必要になったとき、コンデンサから供給してもらうためです。
電流が頻繁に変わりそうなところなどには、至近距離に小型のコンデンサを配備し、そこからなるべく近いところに大きなコンデンサをところどころにつけておきます。
パソコン関係の回路などをみると、IC,LSIの周りに、ゴマよりも小さな、黄色がかった灰色の部品がいっぱいついていますが、ほとんどはコンデンサ(小)です。最近では、LSIの裏側、上面につけてあることも一般的です。その周りに、小さな筒型の部品がありますが、これが大きめなコンデンサの可能性があります(円筒の部品は案外多い)。
このページ、ここで終了。
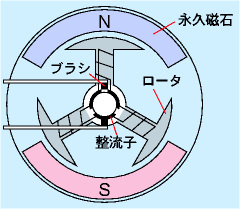
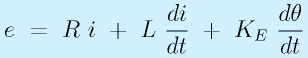
![]() (KTはトルク定数)
(KTはトルク定数)![]()
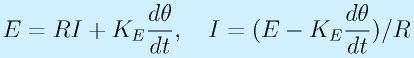
![]()
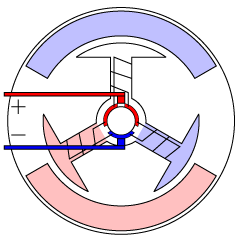
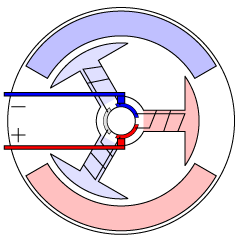
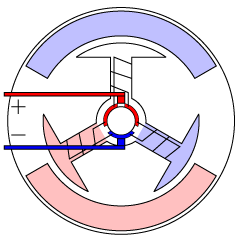
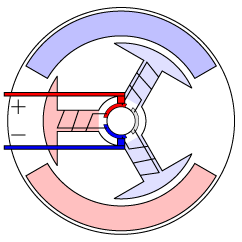
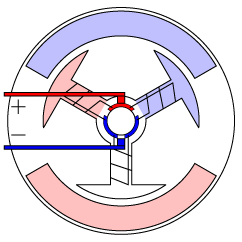
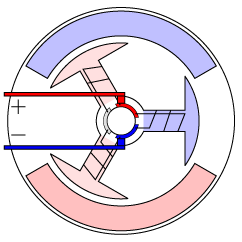
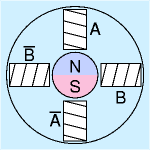
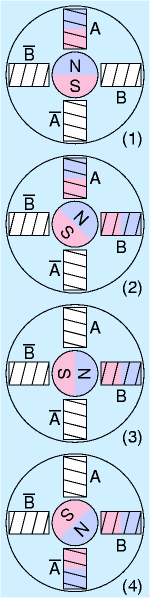
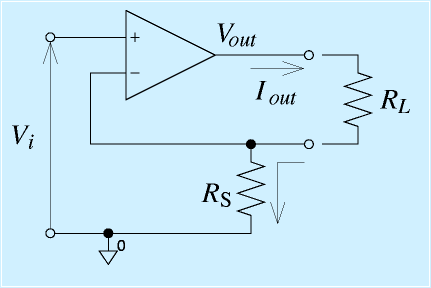 電圧駆動の場合、基本的には、オペアンプによる増幅回路と原理的にはなんら変わりありません。
ただ、ふつうのオペアンプをつかうと、電流が足りないのでモータが回る前にオペアンプの出力が低下するか、熱くなるか、壊れるかします。
電圧駆動の場合、基本的には、オペアンプによる増幅回路と原理的にはなんら変わりありません。
ただ、ふつうのオペアンプをつかうと、電流が足りないのでモータが回る前にオペアンプの出力が低下するか、熱くなるか、壊れるかします。