抵抗変化型センサの使い方
抵抗値が変化するタイプのセンサには、ポテンショメータ(角度、位置)、ひずみゲージ(歪み)、MRセンサ(磁気)、CdSセル(光)などがあります。
抵抗の変化は回路で伝えることができませんので、まずは電圧に変換します。
電圧に変換する場合、
・多くの場合は、抵抗による、基準電圧の分圧
・まれに、定電流電源→抵抗→電圧
という使い方がなされます。
ポテンショメータ
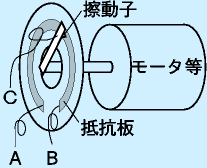 ポテンショメータは直訳すると「分圧計」ですが、多くの場合は角度センサで直線のものもあります。
一般には、角度や移動量に比例して抵抗値が変化するようにつくられています。
ポテンショメータは直訳すると「分圧計」ですが、多くの場合は角度センサで直線のものもあります。
一般には、角度や移動量に比例して抵抗値が変化するようにつくられています。
回転角度型のものは右の図に示すような構造になっていて、扇形の抵抗板と、回転軸に取りつけられそれをこする擦動子(接点)からなります。抵抗板は端から端まで均一に抵抗が分布しています。
抵抗板端から端までをR[Ω]、軸を回転させたときの、A側の端を角度ゼロ、B側端を角度θmax、接点の位置をθとすると、A−C間抵抗 RACおよびBC間RBCは、
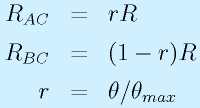
で与えられます。ここで、B−A間に適当な電源Vrefをつなぐと(一般には精度が管理された直流電源:基準電源回路)、電圧C−Aは、
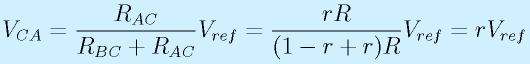
となり、角度に比例した電圧が得られます。
一般にポテンショメータ本来の抵抗値はそれほど低くないため、出力端子から電流が流れ出すと影響が出ます。 そのため、ボルテージフォロワ、非反転増幅回路などで受ける必要があります。
※磁石とMRセンサを用いた非接触のものもあり、寿命が長く、軽く動きます。
※転じて、ただの可変抵抗器をポテンショと呼ぶことがあります。
※実際には、接触部が瞬間的に浮く危険性もあり、適当にコンデンサを並列したり、計測に影響を与えない程度の高抵抗を出力とGNDや基準との間にいれ、宙ぶらりんになることを防ぎます。
CdS、サーミスタ
CdSというセンサは、光センサの一種です。光センサは電流出力なものが多い中で、珍しく抵抗変化です。 また、半導体光センサと異なり、広い範囲の波長、とくに人間の可視光によく反応するため、手頃な明るさセンサとして広く使われています。「暗くなると○○」のたぐい、たとえば街灯などはCdSによることが多いです。
サーミスタは温度で抵抗値が変化するセンサです(c.f.熱電対は温度に比例した電圧、また処理回路などを含む温度センサICもある:LM35が有名)。 熱電対などにくらべて、温度の変化を捕らえやすいため、室温センサなどにつかわれることがあります。
いずれも、抵抗値が変化するタイプで、その抵抗をRf(x)(xは物理量)とおきます。この変化を測るためには、一般には固定の抵抗Roを併用して、やはり基準電源を分圧します。
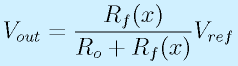
ここで、抵抗の上下を入れ替えると、
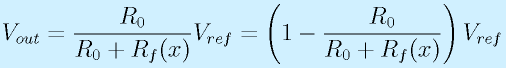
となるため、物理量と抵抗変化の関係、物理量が増えたときに電圧が増えてほしいか減ってほしいか、で、いずれかを選択することができます。
ただし、この方法は結果が非線型になるため(Roが十分大きければ比例としてみなせる)、場合によっては補正が必要です。もっとも、CdSもサーミスタもセンサそのものが非線型なので、いずれにせよ、数値化には校正に基づく変換が必要です。単に「明るくなったら」とか「寒くなったら」という使い方だけがしたければ、コンパレータで比較すれば良いでしょう。
ひずみゲージ
ひずみゲージも抵抗が変化するタイプのセンサです。 具体的にはひずみに比例して抵抗が増減します。 樹脂の薄いフィルムの上に、薄い金属の膜をつけたもので、その膜が伸び縮み(弾性変形の範囲?)することで長さと断面積が変り、抵抗値が変化します(引伸ばすと抵抗値が上がる)。 このような構造であるため、これまで述べたものと比較して、非常に小幅でしか抵抗が変化しないため、扱いにも工夫が必要です。
微少な変化は単純に言えば増幅すれば良いのですが、問題は変化が小さいため、温度変化の影響なども受ける点です。 ひずみゲージ自身も、ふつうの抵抗も温度が変ると抵抗値も変ります。そのため、単純にCdSやサーミスタと同じような回路を用いた場合、ひずみの変化による出力変化なのか、温度変化によるのかが区別できない可能性があります。
そこで、ひずみゲージは一般に4枚、もしくは2枚+通常抵抗2本を組にして、ブリッジ回路という回路を形成して、計測を行います。